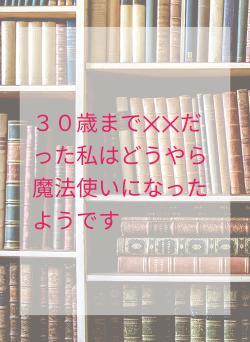「はい、梢です」
『朝早くからごめんね』
「い、いいえ大丈夫です。えっと、なにかあったんですか?」
そう聞くと、少しの沈黙が訪れた。
あたしは嫌な予感がして、まだ部屋にいるお父さんを見る。
お父さんは難しい顔をしたまま何も言わなかった。
『梢ちゃん、落ち着いて聞いてね?』
「え……?」
准一のお母さんの前置きが余計に嫌な予感を覚えさせた。
聞きたくないと、体が拒絶している。
『昨日の夜、准一は家に帰ってこなかったの』
「え!?」
予想外の言葉にあたしは目を見開いた。
眠気はいつの間にかすっかり消え去っていた。
「准一帰ってないってどういう事ですか?」
『あの子、放課後に1人で隣街まで行ってたみたいなの。そこで事故に遭って、病院に搬送されたけれど意識がなくて――』
准一のお母さんの言葉がどこか遠くて聞こえているような感覚だった。
隣街?
事故?
すべての言葉があたしの頭からすり抜けて落ちていく。
説明してもらいたいことが次から次へと生まれて来るのに、ひとつも言葉にならなかった。
受話器片手に呆然としたままでいると、ツーツーと機械音が聞こえてきている事に気が付いた。
いつの間にか電話は切れていたのだった。
『朝早くからごめんね』
「い、いいえ大丈夫です。えっと、なにかあったんですか?」
そう聞くと、少しの沈黙が訪れた。
あたしは嫌な予感がして、まだ部屋にいるお父さんを見る。
お父さんは難しい顔をしたまま何も言わなかった。
『梢ちゃん、落ち着いて聞いてね?』
「え……?」
准一のお母さんの前置きが余計に嫌な予感を覚えさせた。
聞きたくないと、体が拒絶している。
『昨日の夜、准一は家に帰ってこなかったの』
「え!?」
予想外の言葉にあたしは目を見開いた。
眠気はいつの間にかすっかり消え去っていた。
「准一帰ってないってどういう事ですか?」
『あの子、放課後に1人で隣街まで行ってたみたいなの。そこで事故に遭って、病院に搬送されたけれど意識がなくて――』
准一のお母さんの言葉がどこか遠くて聞こえているような感覚だった。
隣街?
事故?
すべての言葉があたしの頭からすり抜けて落ちていく。
説明してもらいたいことが次から次へと生まれて来るのに、ひとつも言葉にならなかった。
受話器片手に呆然としたままでいると、ツーツーと機械音が聞こえてきている事に気が付いた。
いつの間にか電話は切れていたのだった。