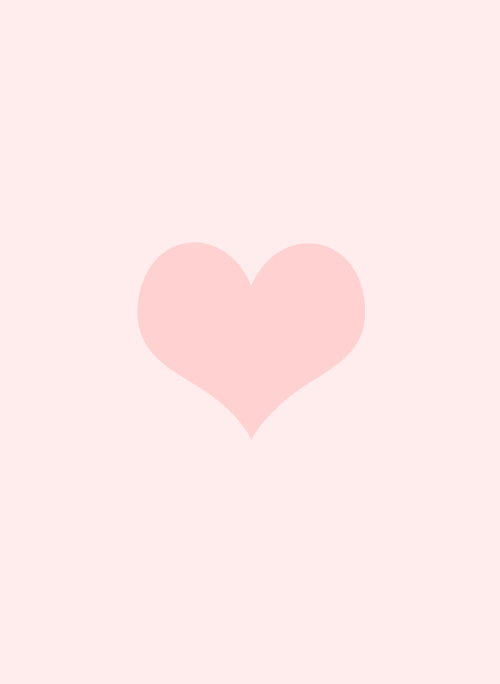「いや、何でもな――」
『ねぇ、知ってた?リーダー。よっちゃん、最近ずっとこの本読んでんの!』
「ちょっ、哲也!」
リーダーが戻ってきたことで、話の矛先をリーダーに向けようとしたのにも関わらず、口の軽すぎる哲也によって俺の策略は棒に振るわれた。
案の定、この話題に興味を示したらしいリーダーは、3人の中心にある俺の本へ近寄る。
『――ああ、コレか。ヨシ、何回目だ?この本読み返すの。』
「ッ……」
周囲のことをよく見ているリーダーには、こんなことはお見通しだったらしい。
だが、誰にも彼女のことも、何故こんなにもあの本を読み返しているのかも話していないから、まだ不幸中の幸いってやつだろう。
本屋で彼女と偶然の再会を果たしたあの日、2冊買った本の一冊。
それを俺は、あの日からずっと何回も何回も読み返している。
中身はただの推理小説。推理小説なんて、1回読み終えれば自宅の本棚に即座にインしていまう俺が、性懲りもなく読み続けているのは、この本を手に取るたび、ページをめくるたびに、彼女のことを思い出せるから。
あの喫茶店で彼女と話したこと
彼女の表情と、彼女の柔らかな声
そして――
知りたくてたまらなかった、彼女の名前。
あの日のことを鮮明に思い起こせてくれるのは、2冊買ったうちの1冊だから。
もう1冊を彼女に渡したことで、あの本を見るだけであの日に起きたことが、勝手に俺の脳内でフラッシュバックするようになったのだ。