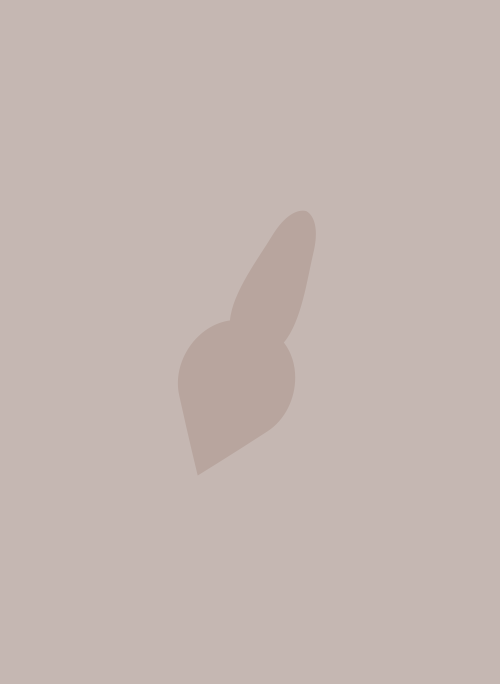「ちょっとリル!これ結び方絶対あってない!」
後ろからパタパタと童顔ミルクティーがやってくる。
同じく対の制服で、ネクタイが結べないらしく顔面に絡まっていた。
「あらあら、きちんと教えたのに…ティンったら私に結んで欲しいのですね」
なんだか嬉しそうなリルが、近寄ってネクタイを結んでいく。
どこの新婚夫婦だ、と内心でルイが毒づいてるのも知らずに、二人の世界に入っていった。
「ち、ちがっ」
「簡単ですよ、こうしてこうすれば…」
「リル、や、め」
真っ赤になって争うティンを物ともせず、綺麗にネクタイを結び終えた。
「ほぅら、完成しましたわ」
「……」
子供扱いされるのが嫌なのか、恥ずかしそうに目線をずらす。
それすらも楽しそうに笑って飛ばすリルに、ルイは疑問を思い出した。
「と、登校とは…」
「学校に行くことですわ。
まさかコスチュームプレイとやらをするためだとでも?」
コスプレのために制服を欲する人間を約一名知っているルイは、黙りこくった。
「あら、報告してなかったかしら。
私向こうで既に編入の手続きを済ませてますの。
電車で数分の私立の高等学校ですわ」
「……え?」
「リル…もう報告したから大丈夫って言ってたのにぃ…」
頭を抱えるティンを尻目に、話を続ける。
「私、日本にいた時に本当に仲良かった友達を探してて…その学校に通ってるみたいなんです。
だから通おうと日本へ。
側近は許可してくださって、協力までしてくださいましたの。
…て、あら?どうなさいました?ルイ・ヒューアンスさん?」
額を抑えてふらりと壁に寄りかかるルイ。
まさか、ここまで行動的な姫様だったとは。
日本に来たのは友達に会うためで、高校まで通うなんて。
こんなのでカサンデュールは大丈夫なのかと思う反面、だから国民から愛されてるのかとも思った。
思い立ったらすぐに行動に移す彼女は、国民から信頼されていて、今や第三皇女なのに好感度一位だ。
さすがというべきか。
「…まさか姫様、電車で学校まで向かうおつもりなのでは」
「大丈夫です!俺路線とか強いですし」
こいつは顔に似合ってバカだった。
頼もしそうに見てるリルもおそれながらバカなのかもしれない。
「仮にも一国の皇女が電車で行くなど許可できません。
私は国からあなたたちの御身を預かっているのですから」
「ええ…」
泣きそうな顔をされる。
う、と良心を掻き毟られ、いそいで訂正を入れる。
「だから、お送り致します。せめて送り迎えを手配させてください」
そういうと、嬉しそうに目を細めた。
「申し訳ありません、助かります」