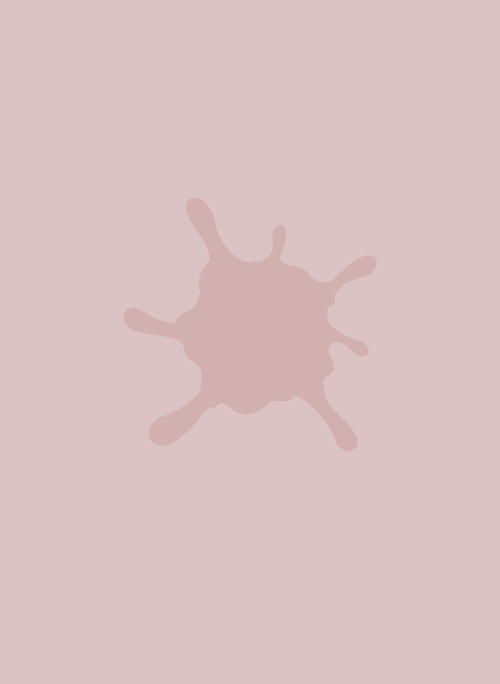ボクの視線に気付いたのだろうか、ひとみさんは顔を上げた。
そして、彼女の肉感的な唇が動く。
「駿平君、美味しかったよ、ご飯。ごちそうさま」
内心動揺してしまう。
彼女の唇を見るたび、その感触を思い出してしまうからだ。
ボクは素っ気ないフリで軽く頷くことしか出来なかった。
いったい、ひとみさんにとって、ボクってなんなんだろうか。
そんなことを考えつつ、ボクは彼女の使った食器を流しに運んだ。
今日は、家庭教師のアルバイトの日だった。
そのことをひとみさんに伝え、家を出た。
その際、彼女は少し寂しそうな表情を浮かべた。
本当に、寂しがり屋なんだな。
多分、ボクにキスしたことだって、なんとない寂しさからなんだろう。
きっと、彼女の服装も、そんな彼女の内面を隠すためのものなんだろう。
ボクは勝手にそんなことを思った。
そして、ふと思う。
ボクはどうして、こんなにも、ひとみさんのことを考えているのだろう、と。