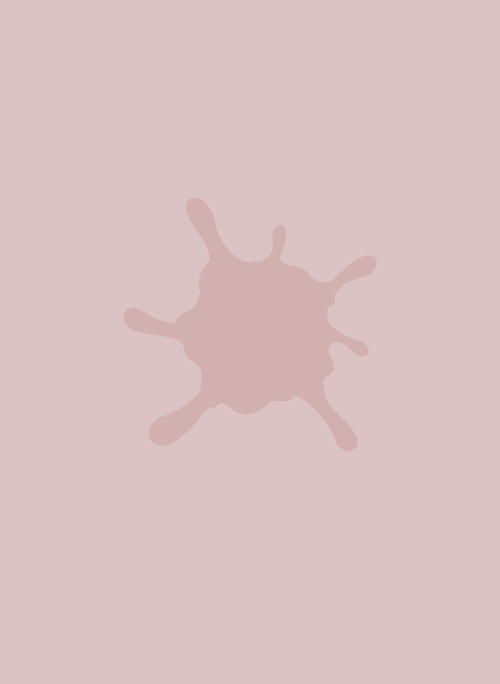自分しか入る事の出来ない部屋の前にこんな物を放っておいたなら、そこからまた疑いがかけられる。
そう思うと守は、渋々少し腰を曲げるとそのペットボトルを手に取り部屋の中へと入っていった。
部屋に入ると一直線にワークチェアへと向かう。
背凭れにしっかりと背を預ける様にドスンと腰を下ろすと同時に、手に持っていたペットボトルは目の前の机の上へ。
……疲れた。
そんな気持ちと共に座った途端にどっと押し寄せてくる疲労感。その為か、守の額からツーっと一筋の汗が流れた。
ふと机の上へと目を向けると、薄暗い部屋のせいで黒へと色を変えたお茶がペットボトルの中でゆらゆらと揺れている。
その揺れが守の喉の渇きを刺激する。
「そういえば、……喉、……渇いたな」
ペットボトルを手に取ると、ちゃぷん…というお茶が波立つ音が響く。
俺は悪くない。
仕方なかったんだ。
俺は……、悪くない。
目を伏せ一度そう自分に言い聞かせると、ペットボトルの蓋を開け、一気にお茶を渇いた喉へと流し込んだ。