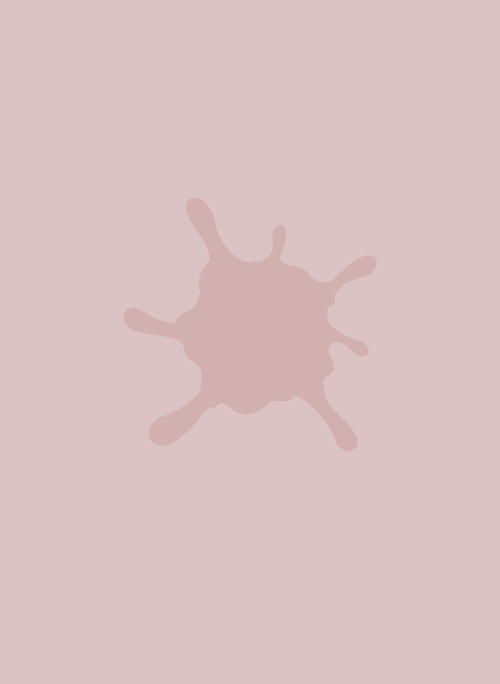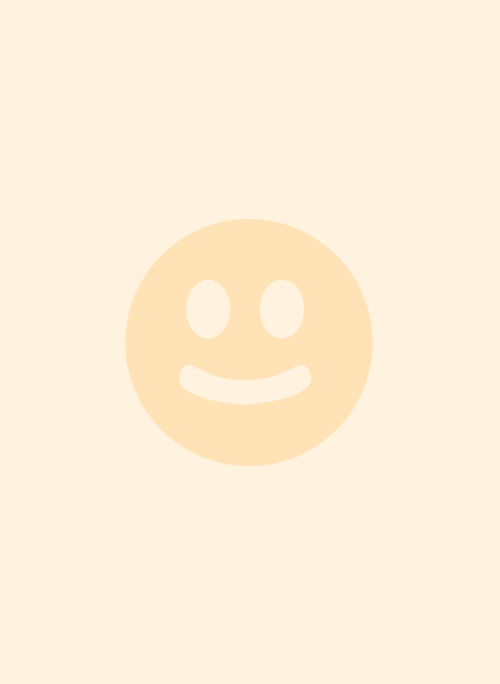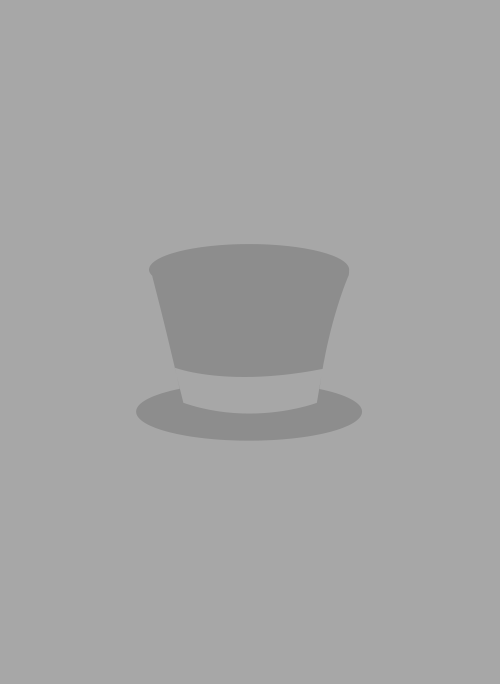復習のような講義が続く大学一年の退屈な時間を過ぎ、大学二年生になって専門用語を習いはじめた。
そんな講義を聞くのが楽しくて、知識の全ても新鮮で、私は高揚感を覚えていた。
けれどどこかに物足りなさも感じていた。今だけしかない一時の煌めきともいえる時間を欲していたのかもしれない。
「ねえ、早紀。来週の土曜日の予定ってあいてる?」
講義が終わって一息吐こうとした時、親友のミドリが訊いてきた。
「あいてるけど……何かあるの?」
「みんなでカラオケに行く予定があってさ。友達が誰か誘ってこいって言うのよ。メンツ足りないって」
聞いた私は何となくミドリの思惑に気づいた。昨日、必死になって友達を呼びとめていたのを知っている。どうやら、そのお鉢が回ってきたらしい。
「また、彼氏さがし? まだ私たち学生だよ。それなのに……」
「なに言っているのよ。学生は学生でも医大生じゃない。今、恋しないでどうするの! 六年勉強、医師国家試験受けて二年間の研修。一人前になる頃には、おばさんだよ。行き遅れになる前に確保しないと」
ミドリの考えも尤もだけど、恋を追う執着心は異常だと思う。行き遅れる前に確保って。物じゃあるまいし。
「土曜日はあいているからいいけど……私は恋人さがしなんてしないよ」
「だから早紀のこと大好き! メンツは上々だから安心して」
ミドリは返事を聞くと、他の人たちも誘っていた。
メンツは上々って。私の話を聞いてくれていたのだろうか。
文句を言おうにも言える性格でもなくて、口を閉ざすしかない。何となく溜め息が出た。
私は男の人と話した経験がすくないし、恋に関しても及び腰だ。誘いがあっても断るのがほとんど。今回は親友のミドリの頼みだからという理由がある。だから時々、積極的なミドリが羨ましかったりもして――。
ふと、ミドリが話しかけるメンバーの中に知らない顔が見えた。猛アピールしているのが目当ての人なんだろうけど、距離をおいて皆を眺めている彼の印象は他の人とは違う。
あんな人いたっけ? あまり話さない人なのかな。同じ講義を受けてきているはずなのに、気づかないなんて私はどうかしている。
惚けていると、見ていた彼が立ち上がった。そして私のほうに歩いてくる。
えっ、どういうこと。目が合っただけで苛立つ人だった?
慌てて逃げるのも変なので、帰り支度のふりをする。残っているのは筆記用具だけなんだけど。近づく足音に鼓動が高まる。鼓動が頂点に達した時、彼の足音がとまった。
「もしかして、前沢?」
苗字を言い当てられて驚く。ミドリが教えたわけじゃないだろうし。
というか、目当ての男性を端からマークしているミドリが、自ら私を紹介してくれるはずがないような気もする。
「中学の時、眼鏡にしたよな。コンタクトにしたのか。涙ボクロでわかったよ」
泣き虫だと思われる涙ボクロが嫌いだった。それを言われてすこしムッとしてしまう。
「確かに前沢早紀ですけど、あなたは――」
誰? と言いかけたところで、ようやく目の前の男性と記憶の顔が重なった。
「えええっ、もしかして加賀くん? えっ、だって、嘘っ! ありえない!」
動揺して、とんでもないことを続けざまに言ってしまった気がする。
けれど懐かしくて、そしてすごく意外で驚くことしかできなかった。
「ひどい言いかただな。確かに成績悪かったけどさ」
「遠くに引っ越したって聞いたから、まさかここで逢うとは思わなかったし……それで、みんな元気?」
言った途端、加賀くんの視線が暗く落ちた。同時に訊いてはいけないことを訊いた気がして続きを話せなくなってしまった。
「親父が四年前にガンで……それから医者になろうと考えてさ。勉強したんだよ」
加賀くんのお父さんの笑顔が頭に浮かんだ。とても気さくなおじさんで、釣りに連れて行ってもらったことがある。そのお父さんが亡くなったんだ。
「ごめんなさい。訊いちゃいけないことだったね」
「いや、故意じゃないだろ。それに今日は早紀に逢えて嬉しいし……というか、変わってないな。お前」
何故かハンカチを渡される。再会で感極まって泣いてしまっていた。子供の頃、『泣き早紀』と言われていたことを思い出す。涙を拭き終わると加賀くんのハンカチだと改めて気づいて、紅潮するのを感じた。
「こうやって話すのって何年ぶりかな」
「中学の時、そんなに話さなかったもんな。と、いうことは十年くらいか」
私の家は加賀くんの家の隣で幼馴染みだった。
けれど、中学生になると離れはじめて。それは級友にからかわれるのが嫌だという理由で。
中学二年になった頃、加賀くんが引っ越すということを親から聞いた。
お父さんの転勤らしく、逢える場所ではない遠いところに行ってしまうとわかった。
見送ると泣いてしまいそうで。今更、好きだったとも言えないで。
「元気でね。また逢えるといいな」とだけ書いた手紙を郵便ポストに入れた記憶がある。
悲しくて一晩泣いたのは、ここでは内緒だ。
「断ろうと思ったけど、早紀が行くなら俺も行くかな。一緒に遊びに行くなんて、小学生以来じゃないか」
言われてみると中学に入ってから、一緒に遊びに行くこともしていない。声変りもして背も高くなった加賀くんは、すごく大人っぽくって子供の頃の加賀くんとはやっぱり違って――。
「ちょっと早紀、私を差し置いて話が弾んでいるってどういうこと?」
途中でミドリが入ってきて説明するのに苦労した。
頬を膨らませて「一人減ったー」と叫んだミドリの言葉を聞いて、二人で顔を見合わせる。毒舌ではあるけれど、喜んでくれているのはわかっている。
この後の集まりも加賀くんと一緒ですごく楽しくて。まるで小学生の時みたいに、はしゃいでいた自分がいた。
>>(続き)9ページ目へ
そんな講義を聞くのが楽しくて、知識の全ても新鮮で、私は高揚感を覚えていた。
けれどどこかに物足りなさも感じていた。今だけしかない一時の煌めきともいえる時間を欲していたのかもしれない。
「ねえ、早紀。来週の土曜日の予定ってあいてる?」
講義が終わって一息吐こうとした時、親友のミドリが訊いてきた。
「あいてるけど……何かあるの?」
「みんなでカラオケに行く予定があってさ。友達が誰か誘ってこいって言うのよ。メンツ足りないって」
聞いた私は何となくミドリの思惑に気づいた。昨日、必死になって友達を呼びとめていたのを知っている。どうやら、そのお鉢が回ってきたらしい。
「また、彼氏さがし? まだ私たち学生だよ。それなのに……」
「なに言っているのよ。学生は学生でも医大生じゃない。今、恋しないでどうするの! 六年勉強、医師国家試験受けて二年間の研修。一人前になる頃には、おばさんだよ。行き遅れになる前に確保しないと」
ミドリの考えも尤もだけど、恋を追う執着心は異常だと思う。行き遅れる前に確保って。物じゃあるまいし。
「土曜日はあいているからいいけど……私は恋人さがしなんてしないよ」
「だから早紀のこと大好き! メンツは上々だから安心して」
ミドリは返事を聞くと、他の人たちも誘っていた。
メンツは上々って。私の話を聞いてくれていたのだろうか。
文句を言おうにも言える性格でもなくて、口を閉ざすしかない。何となく溜め息が出た。
私は男の人と話した経験がすくないし、恋に関しても及び腰だ。誘いがあっても断るのがほとんど。今回は親友のミドリの頼みだからという理由がある。だから時々、積極的なミドリが羨ましかったりもして――。
ふと、ミドリが話しかけるメンバーの中に知らない顔が見えた。猛アピールしているのが目当ての人なんだろうけど、距離をおいて皆を眺めている彼の印象は他の人とは違う。
あんな人いたっけ? あまり話さない人なのかな。同じ講義を受けてきているはずなのに、気づかないなんて私はどうかしている。
惚けていると、見ていた彼が立ち上がった。そして私のほうに歩いてくる。
えっ、どういうこと。目が合っただけで苛立つ人だった?
慌てて逃げるのも変なので、帰り支度のふりをする。残っているのは筆記用具だけなんだけど。近づく足音に鼓動が高まる。鼓動が頂点に達した時、彼の足音がとまった。
「もしかして、前沢?」
苗字を言い当てられて驚く。ミドリが教えたわけじゃないだろうし。
というか、目当ての男性を端からマークしているミドリが、自ら私を紹介してくれるはずがないような気もする。
「中学の時、眼鏡にしたよな。コンタクトにしたのか。涙ボクロでわかったよ」
泣き虫だと思われる涙ボクロが嫌いだった。それを言われてすこしムッとしてしまう。
「確かに前沢早紀ですけど、あなたは――」
誰? と言いかけたところで、ようやく目の前の男性と記憶の顔が重なった。
「えええっ、もしかして加賀くん? えっ、だって、嘘っ! ありえない!」
動揺して、とんでもないことを続けざまに言ってしまった気がする。
けれど懐かしくて、そしてすごく意外で驚くことしかできなかった。
「ひどい言いかただな。確かに成績悪かったけどさ」
「遠くに引っ越したって聞いたから、まさかここで逢うとは思わなかったし……それで、みんな元気?」
言った途端、加賀くんの視線が暗く落ちた。同時に訊いてはいけないことを訊いた気がして続きを話せなくなってしまった。
「親父が四年前にガンで……それから医者になろうと考えてさ。勉強したんだよ」
加賀くんのお父さんの笑顔が頭に浮かんだ。とても気さくなおじさんで、釣りに連れて行ってもらったことがある。そのお父さんが亡くなったんだ。
「ごめんなさい。訊いちゃいけないことだったね」
「いや、故意じゃないだろ。それに今日は早紀に逢えて嬉しいし……というか、変わってないな。お前」
何故かハンカチを渡される。再会で感極まって泣いてしまっていた。子供の頃、『泣き早紀』と言われていたことを思い出す。涙を拭き終わると加賀くんのハンカチだと改めて気づいて、紅潮するのを感じた。
「こうやって話すのって何年ぶりかな」
「中学の時、そんなに話さなかったもんな。と、いうことは十年くらいか」
私の家は加賀くんの家の隣で幼馴染みだった。
けれど、中学生になると離れはじめて。それは級友にからかわれるのが嫌だという理由で。
中学二年になった頃、加賀くんが引っ越すということを親から聞いた。
お父さんの転勤らしく、逢える場所ではない遠いところに行ってしまうとわかった。
見送ると泣いてしまいそうで。今更、好きだったとも言えないで。
「元気でね。また逢えるといいな」とだけ書いた手紙を郵便ポストに入れた記憶がある。
悲しくて一晩泣いたのは、ここでは内緒だ。
「断ろうと思ったけど、早紀が行くなら俺も行くかな。一緒に遊びに行くなんて、小学生以来じゃないか」
言われてみると中学に入ってから、一緒に遊びに行くこともしていない。声変りもして背も高くなった加賀くんは、すごく大人っぽくって子供の頃の加賀くんとはやっぱり違って――。
「ちょっと早紀、私を差し置いて話が弾んでいるってどういうこと?」
途中でミドリが入ってきて説明するのに苦労した。
頬を膨らませて「一人減ったー」と叫んだミドリの言葉を聞いて、二人で顔を見合わせる。毒舌ではあるけれど、喜んでくれているのはわかっている。
この後の集まりも加賀くんと一緒ですごく楽しくて。まるで小学生の時みたいに、はしゃいでいた自分がいた。
>>(続き)9ページ目へ