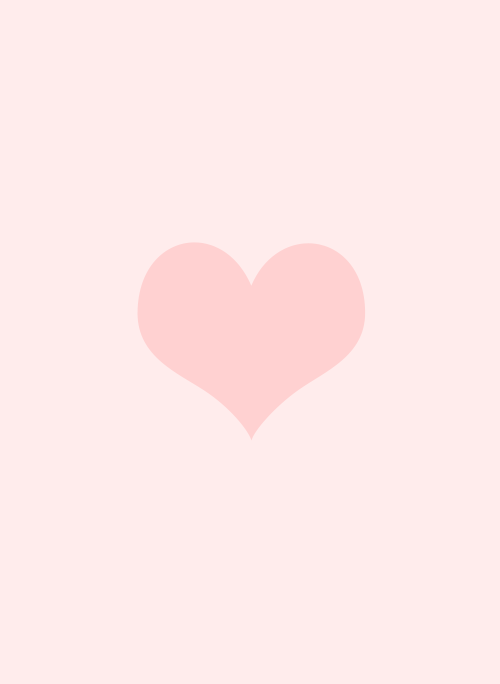「生前は…祖父がお世話になりました…」
…頭を深々と下げてお礼を言った。
その方の後頭部を眺めながら、(ああ、そうか…お孫さんなのか…)と、新ためて気づいた。
でも、その時は何も言えず、バッグから借りてた本を取り出し、手渡すのが精一杯で……。
「…確かに受け取りしました…」
お孫さんの顔をまともに見れないまま、図書館を後にした。
外へ出た途端、大粒の雨が降ってきたのかと思うくらい涙が溢れ出し、泣きながら家に帰ったのを思い出す。
……頼三さんの側で、本を読むながら過ごす毎日を夢見てた。
年齢もかけ離れてたけど、大好きな大好きな人だった。
あの人の話す言葉が聞きたかった。
笑ってる顔が見たかった。
病に倒れてる間、私がどんなに心配してたか、話して聞かせたかった。
…でも、もう…何もできない……。
あの人の声を聞くことも。
優しい声で名前を呼んで頂くことも。
本の感想をお話しすることも。
何を借りればいいか、相談することもーーーー
……何もかも…無くなってしまった。
私の中から、頼三さんが消えてしまった…。
思い出も…
返した本と一緒に…
全部…遠くなってしまった……。
「…ひっ…ふっ…ひっ…ぐっ…」
堪えきれずに、道端にしゃがみ込んで泣いた。
大学四年生の…冬の日のことだった…。
……あれから暫く、私はあの図書館へは通わなかった。
行くのが怖くて、寂しくて、やりきれない気持ちばかりが先立ってたから。
…頭を深々と下げてお礼を言った。
その方の後頭部を眺めながら、(ああ、そうか…お孫さんなのか…)と、新ためて気づいた。
でも、その時は何も言えず、バッグから借りてた本を取り出し、手渡すのが精一杯で……。
「…確かに受け取りしました…」
お孫さんの顔をまともに見れないまま、図書館を後にした。
外へ出た途端、大粒の雨が降ってきたのかと思うくらい涙が溢れ出し、泣きながら家に帰ったのを思い出す。
……頼三さんの側で、本を読むながら過ごす毎日を夢見てた。
年齢もかけ離れてたけど、大好きな大好きな人だった。
あの人の話す言葉が聞きたかった。
笑ってる顔が見たかった。
病に倒れてる間、私がどんなに心配してたか、話して聞かせたかった。
…でも、もう…何もできない……。
あの人の声を聞くことも。
優しい声で名前を呼んで頂くことも。
本の感想をお話しすることも。
何を借りればいいか、相談することもーーーー
……何もかも…無くなってしまった。
私の中から、頼三さんが消えてしまった…。
思い出も…
返した本と一緒に…
全部…遠くなってしまった……。
「…ひっ…ふっ…ひっ…ぐっ…」
堪えきれずに、道端にしゃがみ込んで泣いた。
大学四年生の…冬の日のことだった…。
……あれから暫く、私はあの図書館へは通わなかった。
行くのが怖くて、寂しくて、やりきれない気持ちばかりが先立ってたから。