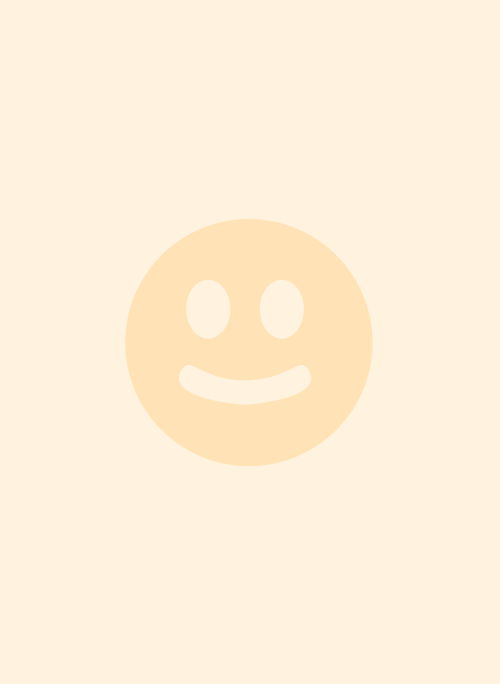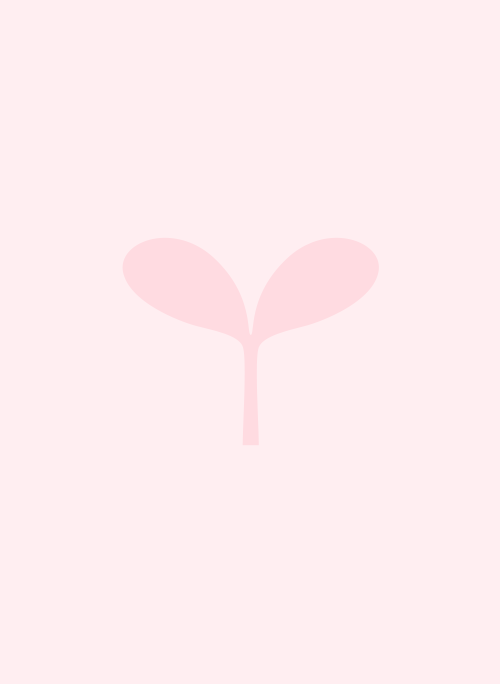アレは、キモチを伝えるだとか確かめ合うだとか、そーゆー甘いモンじゃなかった。
暴いて。
奪って。
貪って。
あらゆる箇所に歯を立て、彼女の白い柔肌に赤い烙印を刻みつけた。
何度も、何度も。
飽くことなく。
萎えることない屹立で彼女を貫き、滾る激情を最奥に打ちつけた。
何度も、何度も。
飽くことなく。
欲望の切っ先で一方的に穿ち続けるようなその行為、まさに蹂躙。
逃げるどころか嫌われちゃってるだろ、コレ。
ソージは深くて長い溜め息を吐き出し、さらに激しく頭を掻き毟った。
だから…
「おはよう、ソージ。」
声をかけられて弾かれたように顔を上げたソージが、目も口もフルオープンのアホ面を晒したのは、無理もないことだろう。
陽に透けてしまいそうな儚げな姿がそこにあった。
蹴破られた扉の木枠に手を掛けて、ダリアが佇んでいた。
「あ、まだ夢の中か。」
ソージがそう結論づけたのもまた、無理もないことだろう。
だって彼女、まーた裸だよ。
今朝は濡れた身体に茜色の振袖を羽織ってるケド、前は開けっパだよ。