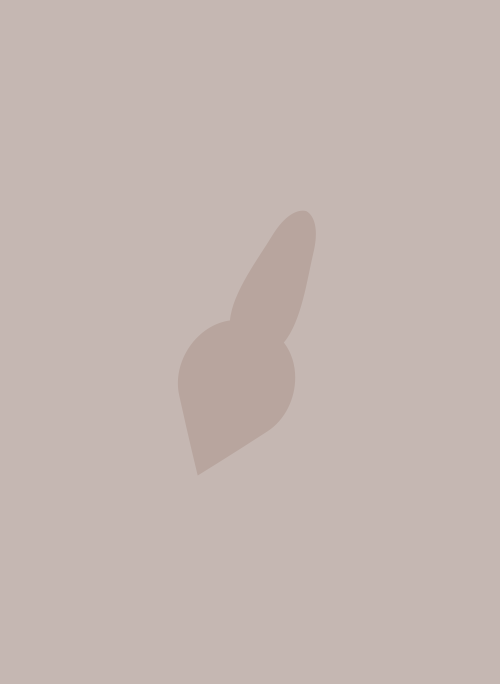「なあ、千晶。
お前…」
ぎゅう、と抱き締められた。
首に細い腕が回って、顔と顔が密着する
女の子特有の柔らかさに、胸がドキンと高鳴った。
「ねぇ、陽、愛してる?」
千晶は好き、千晶は大事。
否、
千晶が好き、千晶が大事。
義務感ではなく、本当に。
「あぁ、愛してる」
「ねぇ、陽?陽は消えない?」
「…?」
何を言ってるか、わからなかった。
でもそれを肯定と受け取った千晶は、満足そうに。
「だよね。
だって陽が好きなのは千晶だもん」
「…え?」
「忘れたの?」
「な、え?」
千晶が好きだから、消えない?
「好きな人が出来たら消えちゃうんじゃ」
「消えないよ」
抱き締めるのをやめて、また頭を撫でられる。
小さい手で、懸命に。
「千晶が好きなら、大丈夫なの。
あ、でも千晶以外を愛したら、死んじゃうよ?
だから――」
また、抱き締められる。
「陽は死なないの。
愛してるんでしょ?」