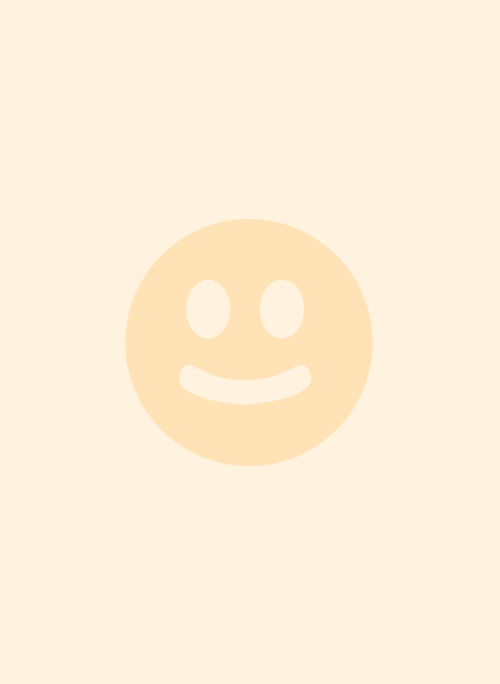「孝太郎くん、何飲む?」
「えっ!? ああ、じゃあとりあえず生で。」
「了解。 あっ、お兄さん。」
千秋さんは声を抑えながら、小声で店員さんを呼び止めた。
「生二つ、お願いします。」
「生二つですね? ありがとうございます。」
俺は今、バイト仲間の千秋さんと二人で飲みに来ている。
このお店は仄かな灯りと黒い壁紙で覆われた、
なんともいい感じのお洒落なお店で、恋人たちや、
それらしき男女が静かにお酒を楽しむような、そんな落ち着いた場所。
なんで俺はこんな店に来てるんや?
しかも千秋さんと二人っきりで。
冷静に考えてもおかしい、これはなんかのドッキリなんやろうか?
俺はどう考えてもこの場に千秋さんといるのが信じられなかった。
それもそのはず、千秋さんは会社でも一二を争う美貌の持ち主で、
同じアルバイト仲間の中でも断トツの人気ぶり。
正社員の人間だって千秋さんを狙っている。
なのにどうして俺と?
どうして千秋さんは俺なんかと飲みに来てるんや?
俺は覗き込むように千秋さんの顔をじっと見た。
「えっ!? ああ、じゃあとりあえず生で。」
「了解。 あっ、お兄さん。」
千秋さんは声を抑えながら、小声で店員さんを呼び止めた。
「生二つ、お願いします。」
「生二つですね? ありがとうございます。」
俺は今、バイト仲間の千秋さんと二人で飲みに来ている。
このお店は仄かな灯りと黒い壁紙で覆われた、
なんともいい感じのお洒落なお店で、恋人たちや、
それらしき男女が静かにお酒を楽しむような、そんな落ち着いた場所。
なんで俺はこんな店に来てるんや?
しかも千秋さんと二人っきりで。
冷静に考えてもおかしい、これはなんかのドッキリなんやろうか?
俺はどう考えてもこの場に千秋さんといるのが信じられなかった。
それもそのはず、千秋さんは会社でも一二を争う美貌の持ち主で、
同じアルバイト仲間の中でも断トツの人気ぶり。
正社員の人間だって千秋さんを狙っている。
なのにどうして俺と?
どうして千秋さんは俺なんかと飲みに来てるんや?
俺は覗き込むように千秋さんの顔をじっと見た。