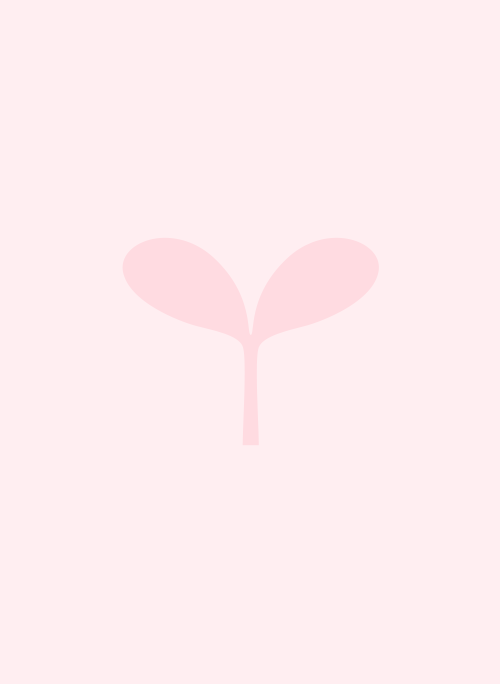それと同時に。
「次からはもっとチョークを投げてみるか」
わざとらしく顎に手をあて、思案する彼の言葉に血の気がひいた亜子は早口で先程のを否定する。
「え、ごめんなさい。石頭じゃないです。自慢じゃないです。あれ本気で痛かったんです。チョークって結構痛いんで止めて下さい、お願いします」
クラス中が彼女が滅多に使うことのない敬語を使ったことに驚き、改めてそれをさせた笹倉に恐怖を抱いた。
因みに恐れる部分が違うというツッコミは受け付けない。
「……そんなに痛かったのか?」
気持ち悪いものを見るような目で亜子を見やる。問いかけられた彼女は首がもげるほど大きく頷いた。
「あ、………先生」
「何だ」
急に頭を縦に振ることを止め、先程よりも青白い顔の亜子に怪訝そうな表情を浮かべる。
「気持ち悪い。吐いていい?」
「…」
「…」
「此処じゃあ止めろ。水道で吐いてこい」
「ラジャッ!」
だだだ、と駆け足で隅まで行き、教室の扉を開いて自分の身体を外に出すと、バタンとそれを閉めて足音は遠ざかる。
「あぁーっ!牛丼がーっ!ラーメンがーっ!出るっ!」
そう叫びながら。
同時に、様々な教室で教師たちが峯ーっ!と声を上げていた。
「……」
笹倉は何も知らぬとでもいうように無言で黒板に向き直り、白いチョークは彼の手により天に昇っていってしまったため、黄色いチョークで
授業を再開したのだった。
【END】