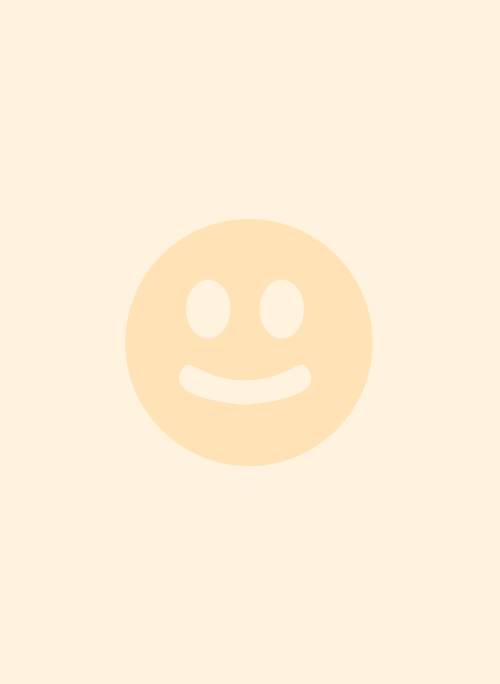*
「ホント、超ラッキー。
こんなかっこいい人がお客さんなんて」
今時の、渋谷風のギャルらしからぬ女が、真紅の唇に笑みを描いた。
ここは街の中枢に位置する市街地で、渋谷にも負け劣らない都市だ。
都市といっても、東京ドーム十数個分の広さしかないところで、
そこを囲んでいるのは、凛とした山々と農地と、古臭い家と煤けた商店街ばかりである。
当然だ。
都市部はこの辺りだけで、本来、この県は田舎なのだから。
その街の、安っぽいホテルの一室で、青年は女と、ベットに腰掛けていた。
「いつもは童貞っぽいサラリーマンとかさあ、キモブタのおっさんばっかりなんだよね。
今日はついてるかもっ」
女の、形の整った唇が上下する。
そんな女の様子を、隣の青年は優しげに眺めていた。
見目麗しい青年であった。
抜けるような色白で、無造作にくねった黒髪を除けば、目鼻立ちも整っている。
娼婦など買わなくとも、充分に女を捕まえられるはずだが、どうしてか、この青年はここに通っている。
「気に入ってもらえて嬉しいよ」
青年はとろけるように微笑んだ。