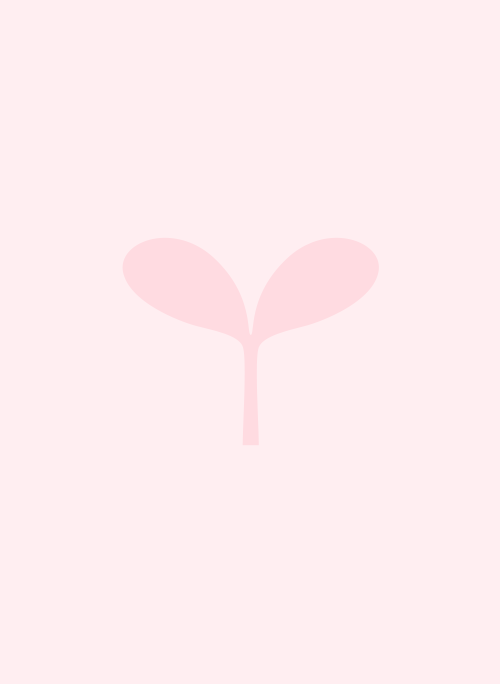「でも、もし君が本当はディオンだと気付かないまま、奴らが精神世界(こころ)に入ってしまえば、ディオン、君が壊れるんだよ」
それでもいいよ、とディオンは言う。
「セリシアが傷つかずに済むのなら、僕は何をされたって、構わない」
そっか、とセリシアは呟く。
悲しいという感情を失った彼女にとって、それしか言葉が見つからなかった。
「雨が止むまで眠るといいよ。大丈夫、僕は、ずっと君の傍にいるから」
「……うん」
ゆっくりと、セリシアは目を閉じる。
「――おやすみ、“ディオン”」
よい夢を、と言って、“セリシア”は優しく、彼の頭を撫でた――。