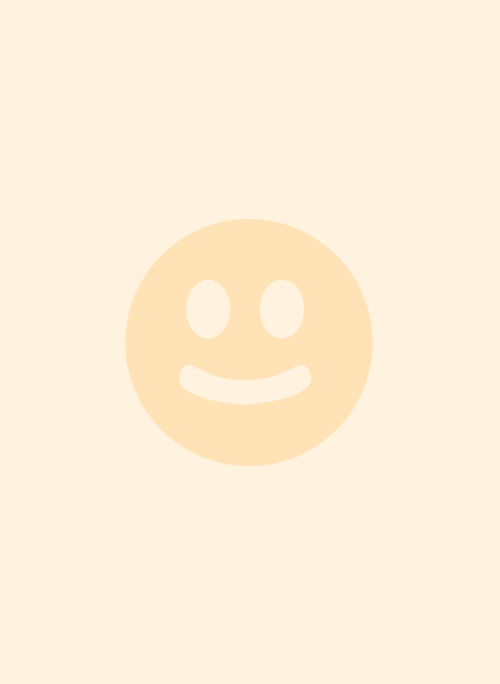「彼女の事ではありませぬ。あの山の事で」
「ふぅん、そこの貴族、何か思い入れでもあるか」
「そのようで」
「それにしても、それくらいで貴族に手を貸すお前も珍しきことじゃな。殺したいほど貴族が嫌いなお前が―――な」
道満の物言いは皮肉や嫌がらせのつもりといった類のものは含まれておらず、珍しく好物を食べない子供に聞くような口調であった。
(貴族が・・・殺したいほど、嫌い?)
明道は道満と目が合い、思わず息を飲む。天冥に怯えているわけでも、道満が怖いわけでもない。
ただ、その張り詰めた空気が、自分はここで喋ってはならない、という圧力となっていたのだ。
何よりも、天冥が明道を見て首を横に二度振ったことが『何も言うな』という無言の圧力だった。
「俺はただ『人の苦しみの上に立ってもなお、人を貶める奴』が嫌いなだけじゃ。たとえ貴族だろうが役人だろうが帝だろうが、俺はそういう人間が嫌い。殺されたやつの中に、貴族が多かった。それだけの話じゃ」
「なるほどぉ・・・で、そこの男はそれに当てはまらなかったという事か」
「まぁ」
「どうせお前の事じゃ。そいつに息子や娘でもおったのじゃろう」