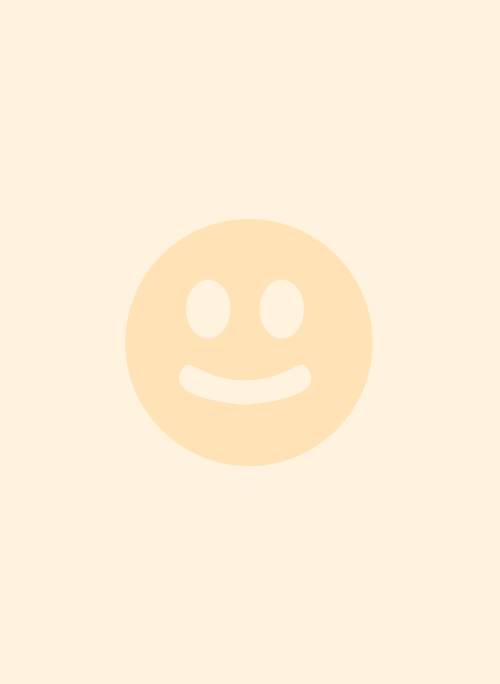時は平安。
ちょうど、藤原(ふじわらの)兼家(かねいえ)が勢力を伸ばしてきた頃の事である。
さきほど天冥が殺したのは、身分が高くとも傲慢な役人だった。だからこそ、天冥が始末したのだ。
いや、勝手に忍び込んだのだが。
天冥は今年で二十三歳になる。
身長は六尺ばかりで長身。その割にはほっそりしていて身体に無駄な肉は無い。目は鋭く吊り上り、唇は具合でも悪いのかと思うほどの紫色だ。
肩より下に伸びた茶髪は、土を焦がした色になっている。
天冥は築地を飛び越えて外に出ると、右京の大宮大路と六条大路の交差点に出る。
ふと前を見ると、丁度、百鬼夜行の途中だった。
化け狐、烏帽子を被った蛙と兎、赤鬼、付喪神(つくもがみ)、多種多様な妖(あやかし)達が大宮大路を通過していく。
あれは、あははの辻だ。
天冥はもちろん、その妖たちの目に留まった。
これが徒人なら(そして妖たちが腹を空かしているなら)即行で喰われているところだが、妖達は天冥を見やると、ギョッと瞠目してゆく足を速めた。
「天冥じゃ」
「あの『外道の貴公子』の?」
「金子を受け取れば鬼おも殺す」
「気に触る人間には容赦なく焼きを入れるだとか」
「ばか。『焼きを入れる』ではなく『焼かれる』だろうが。それを言うなら」
「ああ。あやつは炎の使い手じゃからな」
「恐ろしや」