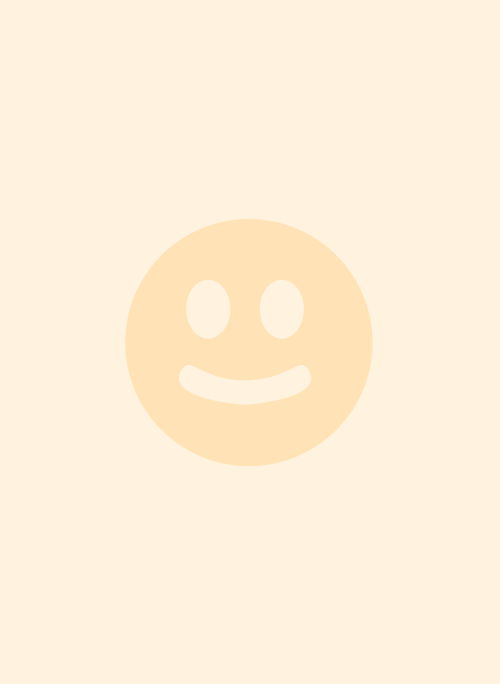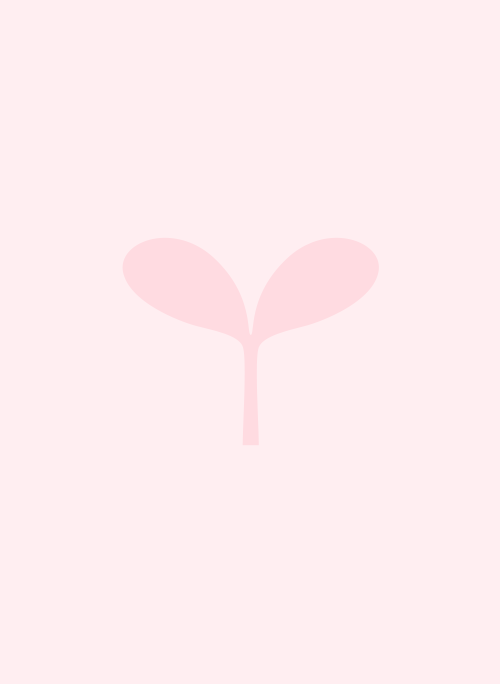創星の言葉を咀嚼につれ、胸が不安にざわめいていく。
「なに……どういう事?」
発した自分が驚くほどに、神妃の声は揺れていた。
そんな神妃をまっすぐ見つめ、創星はまるで日常会話を楽しむように言葉を綴っていく。
「言葉のとおりなんだけどな。神妃は一人っ子で創星なんて少女は最初からいない」
――創星はいない。
がんっ。と鈍器で殴られたような衝撃が全身を襲う。
「嘘だ……嘘だ!!」
「本当だよ、オレは神妃には嘘つかないよ」
「うそ」
「本当だって――」
「矛盾してるよ! 創星が嘘ついてないなら創星はいるはず!! 嘘を吐かないっていうなら、どうして創星がいないなんて言えるの!」
矛盾だらけで本当の事が分からなくなる。むしろ、本当なんてものは最初からないのではと思えても来る。
――目の前の存在が嘘を吐かないなんてことは嘘
――創星がいないなんてことは嘘
――目の前で見つめ返してくるのが創星だったなんてことも嘘
全部ウソだ。
「神妃」
「うそつき、うそつきうそつき!!」
ばふっと音を立てて、創星の顔に枕が当たる。創星はその枕を避けずに受け入れ静かに神妃へ視線を送り続けていた。
その自分とは対照的に落ち着き払った態度へ更に胸に渦巻く感情が膨張していく。
「創星を返して! なんなのよあんた。大っ嫌い!!」
「俺は好きだよ……ずっと昔から」
「わ、私はあんたなんか知らない!! 嫌い。大っ嫌い!!」
「それでも、俺は好きだ」
好きだ――という言葉と同時に、一気に距離を縮められ、神妃は言葉を詰まらせた。驚きに見開かれた瞳には、神妃の驚いた顔を映した藍色の瞳が映っていた。
「神妃がどんなに否定しようとも、”血のつながったお姉ちゃん”はいない。これは本当。俺が嘘を吐かないのも本当。俺はね、ただ好きな子には盲目的に一途なだけだよ」
「どういう――」
意味?
そう問いかけようとした唇に、暖かな指先が軽く触れてきた。
すっと、それが横に滑り目の前の少女の口元へと戻っていく。
「そのうち思い出すよ、きっとね」
内緒話をするように、人差し指が創星の口元を隠す。
どこか蠱惑的なその姿に、ぞくりと神妃の背筋が震えた。
「またわけのわからない事言って……」
思い出すも何もない。自分の目の前にいるのはすべて嘘で塗り固められた人物なんだから、思い出せることなんて一つもないはずだ。
不満を顕にそう言えば、創星はにこりと目を細めた。
「思い出すよ」
「……」
確信に満ちたその声に、神妃は少しだけ信じてしまいそうになった。
その神妃の心の変化に、創星は気づいたようでくすりと笑う。
「何笑ってるのよ」
「なんでもないよ」
「なんでもないのに、笑うなんてことないでしょう」
「じゃぁ、神妃が可愛くて」
「じゃあってなによ」
「なに……どういう事?」
発した自分が驚くほどに、神妃の声は揺れていた。
そんな神妃をまっすぐ見つめ、創星はまるで日常会話を楽しむように言葉を綴っていく。
「言葉のとおりなんだけどな。神妃は一人っ子で創星なんて少女は最初からいない」
――創星はいない。
がんっ。と鈍器で殴られたような衝撃が全身を襲う。
「嘘だ……嘘だ!!」
「本当だよ、オレは神妃には嘘つかないよ」
「うそ」
「本当だって――」
「矛盾してるよ! 創星が嘘ついてないなら創星はいるはず!! 嘘を吐かないっていうなら、どうして創星がいないなんて言えるの!」
矛盾だらけで本当の事が分からなくなる。むしろ、本当なんてものは最初からないのではと思えても来る。
――目の前の存在が嘘を吐かないなんてことは嘘
――創星がいないなんてことは嘘
――目の前で見つめ返してくるのが創星だったなんてことも嘘
全部ウソだ。
「神妃」
「うそつき、うそつきうそつき!!」
ばふっと音を立てて、創星の顔に枕が当たる。創星はその枕を避けずに受け入れ静かに神妃へ視線を送り続けていた。
その自分とは対照的に落ち着き払った態度へ更に胸に渦巻く感情が膨張していく。
「創星を返して! なんなのよあんた。大っ嫌い!!」
「俺は好きだよ……ずっと昔から」
「わ、私はあんたなんか知らない!! 嫌い。大っ嫌い!!」
「それでも、俺は好きだ」
好きだ――という言葉と同時に、一気に距離を縮められ、神妃は言葉を詰まらせた。驚きに見開かれた瞳には、神妃の驚いた顔を映した藍色の瞳が映っていた。
「神妃がどんなに否定しようとも、”血のつながったお姉ちゃん”はいない。これは本当。俺が嘘を吐かないのも本当。俺はね、ただ好きな子には盲目的に一途なだけだよ」
「どういう――」
意味?
そう問いかけようとした唇に、暖かな指先が軽く触れてきた。
すっと、それが横に滑り目の前の少女の口元へと戻っていく。
「そのうち思い出すよ、きっとね」
内緒話をするように、人差し指が創星の口元を隠す。
どこか蠱惑的なその姿に、ぞくりと神妃の背筋が震えた。
「またわけのわからない事言って……」
思い出すも何もない。自分の目の前にいるのはすべて嘘で塗り固められた人物なんだから、思い出せることなんて一つもないはずだ。
不満を顕にそう言えば、創星はにこりと目を細めた。
「思い出すよ」
「……」
確信に満ちたその声に、神妃は少しだけ信じてしまいそうになった。
その神妃の心の変化に、創星は気づいたようでくすりと笑う。
「何笑ってるのよ」
「なんでもないよ」
「なんでもないのに、笑うなんてことないでしょう」
「じゃぁ、神妃が可愛くて」
「じゃあってなによ」