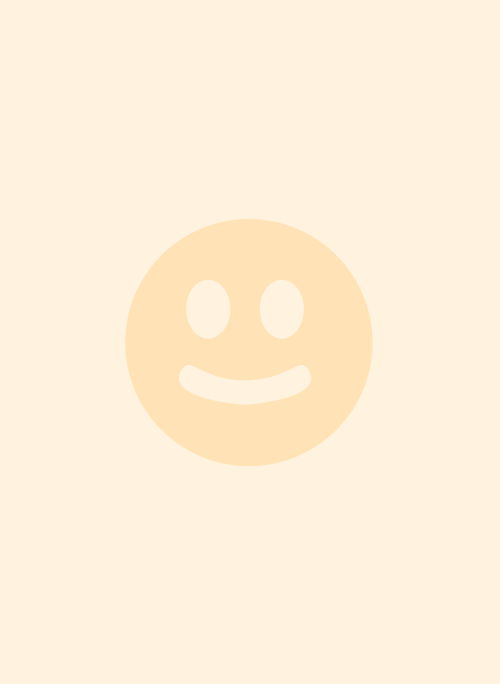ふと、ぼくは自分の家について考える。ぼくの実家は空から降ってきたゾウに押し潰されてしまった。幸い家には誰もいなくて、近くを散歩していた人が散らばった木材に足をひっかけて転んだ以外に怪我をした人はいなかった。だけど家は一から建て直す方が楽ってくらいにズタズタに壊れてしまった。
ぼくにとってもそれは悲しい出来事だったけど、母ほど悲しみに暮れることはなかった。
母は泣いた。
ぼくは泣かなかった。
母にとっての家とぼくにとっての家は、一体何が違ったんだろう?
ぼくは降ってきたゾウを売り払いその金で一人暮らしを始めた。ゾウは近年稀にみるほど立派なゾウだったので(なんといってもぼくの家を一撃で木端微塵にしたのだから)かなり良いアパートを借りられた。母と二人で住む筈だったその部屋は一人で住むには些か広すぎたけど今はもう慣れた。
母がいない理由は単純で、母はゾウを憎むあまりハンターになったからだ。だから母は一年の大半はどこか遠い国にいて、そのうちの半分以上は気違いみたいに銃弾をばらまいている。
母の家は失われたのだ。ぼくが苦労して探し出した日当たりの良い小綺麗なアパートなんかじゃ代わりになれない。
でもぼくは違う。
ぼくは新しい家をしっかりと自分の家にしていかなければいけない。自分を家にコミットさせなければいけない。或は家を自分に。
ぼくはギリギリの所でまだ失っていない。絶望もしていない。気違いみたいに銃弾をばらまく必要はない。
母の話を田中にすると身体をぶるっと震わせ、毛を逆立てて、
「恐ろしい話ですね」
とだけ呟いた。ゾウが降ってきて家を壊したことに対する言葉なのか、母がハンターになって信じられない数の動物を撃ち殺していることに対しての言葉なのかは判然としなかったが、確かにこれは恐ろしい話だと自分でも思ったので追求はしなかった。
それからぼくは「着きやしたぜ」と田中に起こされるまで眠った。随分深く。
重い瞼を擦り、タクシーの窓から外をみるとそこは白い部屋だった。長細い部屋だ。幅はタクシー一台分程で、だから部屋にタクシーが嵌まっているような感じがする。だけど長すぎて両端が見えない。タクシーの前にも後ろにも延々と白い空間が続いている。壁際には長椅子が置いてあり、そこには何人もの人が座っていた。
ぼくにとってもそれは悲しい出来事だったけど、母ほど悲しみに暮れることはなかった。
母は泣いた。
ぼくは泣かなかった。
母にとっての家とぼくにとっての家は、一体何が違ったんだろう?
ぼくは降ってきたゾウを売り払いその金で一人暮らしを始めた。ゾウは近年稀にみるほど立派なゾウだったので(なんといってもぼくの家を一撃で木端微塵にしたのだから)かなり良いアパートを借りられた。母と二人で住む筈だったその部屋は一人で住むには些か広すぎたけど今はもう慣れた。
母がいない理由は単純で、母はゾウを憎むあまりハンターになったからだ。だから母は一年の大半はどこか遠い国にいて、そのうちの半分以上は気違いみたいに銃弾をばらまいている。
母の家は失われたのだ。ぼくが苦労して探し出した日当たりの良い小綺麗なアパートなんかじゃ代わりになれない。
でもぼくは違う。
ぼくは新しい家をしっかりと自分の家にしていかなければいけない。自分を家にコミットさせなければいけない。或は家を自分に。
ぼくはギリギリの所でまだ失っていない。絶望もしていない。気違いみたいに銃弾をばらまく必要はない。
母の話を田中にすると身体をぶるっと震わせ、毛を逆立てて、
「恐ろしい話ですね」
とだけ呟いた。ゾウが降ってきて家を壊したことに対する言葉なのか、母がハンターになって信じられない数の動物を撃ち殺していることに対しての言葉なのかは判然としなかったが、確かにこれは恐ろしい話だと自分でも思ったので追求はしなかった。
それからぼくは「着きやしたぜ」と田中に起こされるまで眠った。随分深く。
重い瞼を擦り、タクシーの窓から外をみるとそこは白い部屋だった。長細い部屋だ。幅はタクシー一台分程で、だから部屋にタクシーが嵌まっているような感じがする。だけど長すぎて両端が見えない。タクシーの前にも後ろにも延々と白い空間が続いている。壁際には長椅子が置いてあり、そこには何人もの人が座っていた。