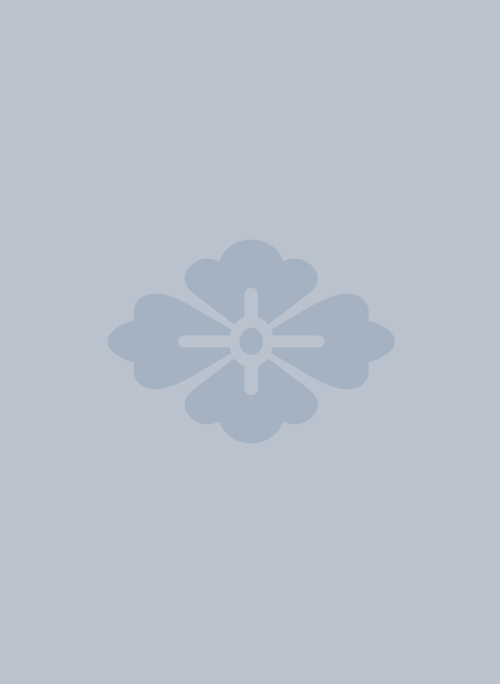彼は、生まれながらの『王子』だったから。
どんな災厄の渦中に投げ込まれようとも。
どんな不幸が彼の身を犯そうとも、弱音を吐くことは許されなかった。
もし、彼の側に、牢番が一人でも付き添っていたのなら。
キアーロは鎖で縛られた、痛みのための吐息をつくことさえできず。
最大の虚勢でもって、苦痛を笑って耐えなければいけないはずだった。
……だから。
「……ま……だ」
マシか。
痛みを、痛い、と呻くことが出来る分だけ。
声がまともに出なくなるほど、弱り切り。
ココロの中で、そう、うそぶくキアーロのすぐそばを、水滴が落ちる。
特別な一滴ではない。
地上に降った雨が、地面に落ちて。
彼が捕らえられている地下牢まで染み込んだ、ただの水だった。
けれども。
それは、彼にとって、命の水に等しかった。
この地下牢に、水滴がしみこむほど雨が降った、ということは。
雨神が、生贄であるキアーロ王子を気に入った、という証だったから。
どんな災厄の渦中に投げ込まれようとも。
どんな不幸が彼の身を犯そうとも、弱音を吐くことは許されなかった。
もし、彼の側に、牢番が一人でも付き添っていたのなら。
キアーロは鎖で縛られた、痛みのための吐息をつくことさえできず。
最大の虚勢でもって、苦痛を笑って耐えなければいけないはずだった。
……だから。
「……ま……だ」
マシか。
痛みを、痛い、と呻くことが出来る分だけ。
声がまともに出なくなるほど、弱り切り。
ココロの中で、そう、うそぶくキアーロのすぐそばを、水滴が落ちる。
特別な一滴ではない。
地上に降った雨が、地面に落ちて。
彼が捕らえられている地下牢まで染み込んだ、ただの水だった。
けれども。
それは、彼にとって、命の水に等しかった。
この地下牢に、水滴がしみこむほど雨が降った、ということは。
雨神が、生贄であるキアーロ王子を気に入った、という証だったから。