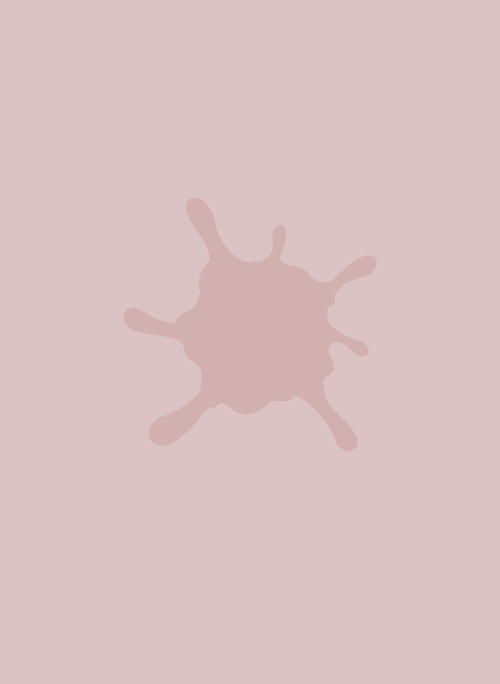「鈴木君さ、学校の時と感じ違うよね」
ある日、いつものようにやってきた委員長が、ふとそんなことを漏らした。
学校の時、と言っても僕が彼女と言葉を交わしたのは数えるほどしかなかったと思うのだが。
「……そう?」
空いたコップに麦茶を注いでやりながら、僕は答える。
「なんていうか、もっと愛想よかった気がする」
そりゃまぁ、ある程度は愛想よく振舞わないといけなかったからだ。
ドラマやマンガ。どうでもいいことばかりを話題として用意して。
楽しげに会話に加わらなければいけなかった。
独りが好きだ、と言っても、あの場所はそれを許してはくれない。
と言っても、僕の場合はほとんど作り笑いでやり過ごしていたわけだが。
ある日、いつものようにやってきた委員長が、ふとそんなことを漏らした。
学校の時、と言っても僕が彼女と言葉を交わしたのは数えるほどしかなかったと思うのだが。
「……そう?」
空いたコップに麦茶を注いでやりながら、僕は答える。
「なんていうか、もっと愛想よかった気がする」
そりゃまぁ、ある程度は愛想よく振舞わないといけなかったからだ。
ドラマやマンガ。どうでもいいことばかりを話題として用意して。
楽しげに会話に加わらなければいけなかった。
独りが好きだ、と言っても、あの場所はそれを許してはくれない。
と言っても、僕の場合はほとんど作り笑いでやり過ごしていたわけだが。