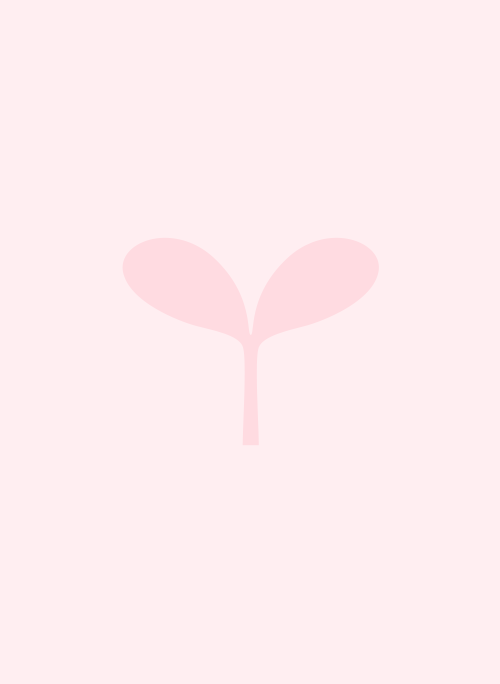遠足に出かける前の学童のように、わくわくしながらゴリラが僕の隣で歩いている。今日は京香のマンションでのお泊まり会なのだ。
「お前、そんないっぱい荷物持って何泊するつもりなんだよ」
諒太は何を訊いてもニコニコしている。すっかり京香に骨まで抜かれているようた。
「でもさあ、初めてお泊まりするのになんでヒロもいるんだよ」
「え? じゃあ僕帰ろうか?」
「いやいやいやいや! お願いだから帰らないで」
「だろ?」
「うん。二人きりなんて無理。お願い、ヒロちゃん。一緒にいて」
骨抜きゴリラってのはこうもなよなよになるものなのだろうか。文化部最強のアスリートが聞いて呆れる。
――ところで……。「ヒロちゃん」てなんなんだ。
地図アプリを開き京香のマンションを探す。
「え? このマンション? すっげ! 流石お嬢様」
やっぱりお前に彼女は釣り合わないよ。と続けたかったけれどぐっと堪えた。諒太を応援しなきゃ。
エントランスの自動ドアをくぐるともう一つ自動ドアがある。オートロック式のマンションのようだ。
――805『呼』
四つボタンを押すと透き通った声がインターホンから流れてきた。
「はーい。どうぞー」
するとさっきまではぴくりとも動かなかった二つ目の自動ドアが高級そうな静かな音をたて開いた。
エレベーターに乗り八階で降りる。一番手前の部屋が801。どうやら京香の部屋は一番奥のようだ。802号室の前まで進むと、時間を見計らっていたかのように京香が玄関のドアを開けた。
いつもの人懐っこい笑顔で「いらっしゃい。こっち、こっち」と手招きをしている。ポニーテールにエプロン姿。見た事のない京香の姿に僕ははっとした。
僕以上に興奮しているやつが、僕の後ろにいる。決して後ろを振り向いて諒太の姿を見た訳ではない。けれど、諒太の興奮ははっきりと感じとれたのだ。
鼻息が……荒い。
「お邪魔しまーす」
部屋に入ると廊下の先に広そうなリビングがちらりと見える。一体家賃はいくらするんだろう。そんな疑問を持ちながらリビングに入る。
「広っ!」
僕は思わず叫んだ。
「うわっ! このリビングだけで俺のアパートの部屋とトイレとキッチンとバスルームを合わせた面積より広い」
諒太のアパートには何度も遊びに行った事がある。正に諒太の言うとおりの広さだった。
「家賃、いくら?」
僕は恐る恐る訊ねた。
「ああ、そう言えば知らない。パパが払ってくれてるから」
それもそのばず。京香の両親はあの「ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団」の奏者だった。お母さんはバイオリニスト。お父さんはパーカッションの王様――ティンパニ――を叩いている。
音楽家のサラブレッドとしてこの世に生を享《う》けたのだ。
リビングのガラスケースの中には高二の時にソロコンテストで全国一位になった時のトロフィーなど、数々の栄光の品が並べられている。
僕が吹いているアルトサックスは音楽を知らない人でも知っている人が多い。
しかし京香の吹いているユーフォニアム。決して目立つ楽器ではない。一般人には認知度も低いだろう。
ユーフォニアムの奏者は一度はこんな会話をした事があると思う。
『へー、吹部なんだあ。楽器はなに?』
『ユーフォ』
『ユーフォ? 聞いた事ある。でもどんな楽器だっけ?』
『うーん、チューバの小さいやつ』
『へー、チューバってどんな楽器だっけ?』
一般人にはその程度の認知度である。
ユーフォニアムとは、吹奏楽や金管バンドで主に用いられる金管楽器で、B♭管が主流。幾重かに巻かれた円錐管と、通常四つのバルブがあることが特徴なのだ。
音域は「テナー」や「テナー・バス」のトロンボーンとほぼ同じだけれど、それよりも幾分か柔らかく丸みのある音色を奏でることができる。
そう。彼女の音は柔らかく丸みをもっている。なかなか出せる音ではない。
諒太と僕は、リビングの広さだけに目を取られていた。しかしテーブルを見て僕はぶったまげた。
そこには色とりどりの料理が所狭しと並んでいた。
「うわっ! これ、京香が一人で作ったの?」
「どう? 私の女子力、見直した?」
見直すも何もお前凄いんだな。僕がそう言おうとした瞬間、盛りのついたゴリラが叫んだ。
「京香、すげえ! 流石に俺の愛した女だ」
「あ、そういうの、いらないから」
「はい。ですよね」
僕は落ち込む諒太の肩を叩いた後、リュックから赤ワインとシャンパンを取り出した。
「京香、赤ワインは冷やさなくても美味しいから、こっちのシャンパン冷やしといてくれる?」
「おっけ」
高級そうなワイングラスに赤ワインを注ぎ、皆がグラスを持ち上げた。
「じゃあみんなの明るい未来の為に……」
そしてまた諒太が余計な事を口ずさむ。
「それから、俺と京香の明るい……」
すかさず京香がぎっと諒太を睨む。
「あ、ごめんなさい」
京香はぷっと吹き出し「かんぱーい!」と音頭をとった。
「かんぱーい!」
京香の料理はどれもこれも本当に美味しかった。諒太も「うまい」を連発しながらむさぼるように食べていた。僕たちが美味しそうに食べている顔を見て京香も嬉しそうな表情を浮かべている。
「いやー! うまかった。お世辞はゼロでうまかった」
「諒太、ありがとう。さあヒロ、本題に入りましょ。入寮してから毎日見てるのよね? その夢」
「そうだね。あ、でもゴールデンウィークに実家に帰ったんだけど、その間は見なかったんだ」
「て、事わよ、夢を見る条件は『ヒロの寮で寝る事』よね。今日はうちに泊まるんだから今日も夢を見てしまえばその条件は間違いって事になるけど。まあ、そこは明日の朝教えてね」
すると諒太が口を挟んだ。
「それってさあ、『ヒロの寮でヒロが寝る事』なのかな。それとも『ヒロの寮で俺が寝ても』見れるのかなあ」
京香ははっとして、きっと諒太を睨むように目を向けた。諒太はまた怒られてしまうとでも思ったのだろうか。大きな体をきゅっとすぼめた――母親に怒られるのを覚悟した、悪事がバレてしまった少年のように。
「諒太!」
「はいっ!」
「いい所に気づいたわね。その可能性もあるわよね。今度ヒロの寮に泊まってみてよ」
「はいっ! えっ? あ、うん。だね」
悪事がバレずに済んだ少年はほっと胸を撫で下ろした。
「でも私も行きたいな。ヒロの寮。ほら、私って背が高いから髪の毛結んでギャップかぶってマスクすればバレないと思わない? ねえ、ヒロ。いいでしょ?」
彼氏に何かをおねだりでもするかのように甘えた声を出しながらにこりと微笑んでいる。確かに可愛い。諒太が骨抜きにされるのもうなづける。
「まあ、そうだな。170cm以上あるから誰も女だとは思わないか」
「169cmだってば!」
赤ワインの瓶はその役目を終えテーブルの上に立っている。シャンパンの瓶も間もなくその役目を終えようとしている。
といっても僕と諒太はシャンパンを一杯ずつしか飲んでいない。「これ美味しい!」そう言って京香が瓶を抱え込んでしまって以来、僕たちは缶ビールを飲んでいるのだ。
今日ここへ来る前、諒太は眠そうに何度もあくびをしていた。「どうした? 寝不足なのか?」そう訊ねると。子供のような答えが帰ってきた。今日の事が楽しみで朝方まで寝つけなかったらしい。
そんな諒太は既に眠そうな目をしている。元々そんなにお酒が強い訳ではないらしい。京香も頬を赤らめている。
「はい、はい。169cmでしたね」
京香は口を尖らせ頬を膨らませた。