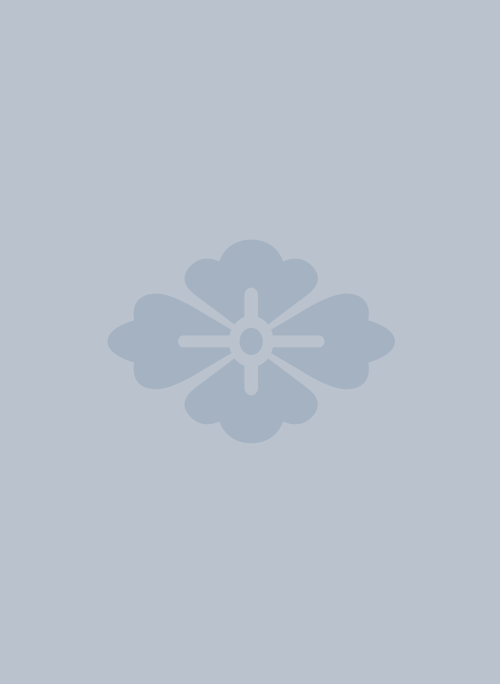夏の甲子園が始まろうとしていた。
野球なんぞ日頃は興もなさげな女子高校生も、この時期ばかりはどこの何番の選手がカッコいいだの、そんな話題で耳目を集める。
しかも。
この年は翔一郎の母校が久々に出場する、というのがすでに決まっていた。
県立の学校だけにやかましくはなかったが、
──応援団への寄付の依頼について。
という封書が何枚も来ると逆に、
(誰が意地でも出すかい)
というあまのじゃくな感情が、翔一郎は湧いて出るのであった。
数日、過ぎた。
どこからか、高校野球のラジオの中継が聞こえてくる。
時折ザーザーと雑音が混ざって、
(ちゃんとチューナー合わさんかいな)
少しだけイラつく。
が。
ジリジリと蒸し暑い京都の夏には少し鬱陶しいノイズながら、逆にないと困る風物詩でもある。
翔一郎に個展の話が舞い込んだのは、そうした時候であった。
持ち込んだのは、若い女である。
「香月愛」
と書かれたポップな花柄の名刺を差し出したセーラー姿の彼女は、「東京で写真を見た」と言った。
「あ、制服の女の子を撮った写真ですやろ」
あれはいわゆる瓢箪から駒っちゅうやつですのや──と翔一郎は苦笑いを浮かべ、
「ですよって個展やるほどのレベルとちゃいますのや」
と、エマが持ってきた麦茶を飲んだ。
「でもあのあと発表された苔庭の写真、雑誌とか取り上げられてますよ」
あれか、と翔一郎はピンと勘が働いた。
雨上がりの朝早くに嵯峨の鹿王院へ行って撮ってきた一枚のことであろう。
「東京じゃあ中々ああいう写真は撮れないので、やっぱり京都の写真家さんでないとああは行かないよねって、話題になってたんですよ」
「まぁあれ宣伝に使うからって撮っただけの話ですよって、おまけに」
京都は素材の宝庫で、素人でもそこそこ撮れるというような話をしてから、
「それだけにプロがやってゆくにはシビアな目もあるし、逆に言うたら京都のプロの写真家は、うちみたいのは別にしてみんな実力が高い…っちゅう話なんですわぁ」
翔一郎は身も蓋もない言い方をした。
「そうなんですか」
「せやから、しっかりリサーチしてかからんと、前に東京から進出してきた大手の事務所みたいに、失敗して都落ちっちゅうことかてあんのですわ」
「でもそれで成功したら、スゴくないですか?」
「そら成功したら、の話ですわな」
まぁ個展の話は目一杯考えときましょ──というと、香月愛というその謎の女は帰って行った。
「…個展、するの?」
エマが麦茶を下げに来た。
「あー…エマは覚えといた方がえぇから教えとくけど」
考えときましょ、は分かりやすく言うとお断りの合図なのだ…と翔一郎は言い、
「気を遣ってやんわり断るのも、まあ京都式の社交術やな」
十年以上も暮らすと嫌でも身に付くものであるらしかった。
送り火の済んだ頃、一誠に借りていた資料を代わりでエマが返しに行くことになり、自転車で烏丸御池の陣内事務所まで駆ったことがある。
「エマちゃんが来るとは珍しいなあ」
陣内一誠は打ち合わせから戻ったばかりらしく、シュッとしたスーツを着こなしていた。
「饗庭が借りていた資料を返しに来ました」
「わざわざサンキュな」
一誠は受け取った。
「あんまり顔見んけど最近の翔一郎はどや?」
「相変わらずバタバタ走り回ってます」
一誠は吹き出した。
「あいつ、仕事は出来るし手際も悪くはないんやが、少しだけイラチで神経質なとこがあってやな」
そういう生まれ持った中身は変わらんようやな、というと包装に入った八ッ橋をエマに渡した。
「おもろいこととか、なかったんか?」
「面白いかどうかは分からないんですけど」
とエマは、香月愛が西陣に来た話をした。
「あー…あいつか」
「陣内さんの知り合いなんですか?」
「まぁな。悪い子やないんやが、ちょっと色々ある子やからな」
翔一郎に今度話せる機会があったら話しとく、といい、その日は西陣に戻った。
夏休みが明けた最初のスクーリングの日、いつものように自転車で、エマが二条城の堀端にある通信制の高校へ行くと、この日から新しく編入する生徒が来る、というのでソワソワした空気に、教室は変わっていた。
特に男子の生徒が、
「女子らしいけどベッピンなんやろか」
とはしゃいでいる。
(そういえば)
エマが初めてスクーリングに来た日も、男子は騒いでいて担任が怒鳴った記憶がある。
(いつのときも男子って子どもだよね)
エマは少し懐かしかった。
国士舘で剣道をやっていたという、獅子舞の頭のような顔をした担任が教室に入った。
「今日から新しい生徒が加わる」
と獅子頭が言うと、
「…はい」
蚊の鳴くようなか細い声でおずおず引き戸を開けた。
視線を向けると、
「…あ」
驚いた。
無理もない。
先だって個展の話を持ち込んできた香月愛なのである。
だが。
愛は気づかない。
(気づかない方がいい場合もある)
少し伏し目がちのエマはそのまま、遣り過ごそうとした。
しかし。
愛が何かに気づいた様子で、
「あっ」
と声をあげた。
エマが視線を上げると、
「饗庭お前、香月と知り合いか?」
担任が訊いてきた。
エマがいや、あの…と口ごもると、
「まあ詳しくは知らんけど、知らん訳でもないようやから…香月、饗庭の隣に座れや」
「はい」
愛はエマの隣に座った。
「ほな教科書、三十五ページ開きや」
カリキュラムはさりげなく始まったのであった。
放課後。
エマが帰り支度を始めていると、
「エマちゃん」
素敵なお兄さんね──と愛は声をかけてきた。
「あれは兄じゃないの」
主人なの、とエマが言うと愛はさすがに驚いた様相になったが、
「まるでドラマみたいな夫婦だね、女子高生の奥さんなんて」
「そうだよね」
でも羨ましいな──と愛は呟いた。
「?」
「先生にさっき聞いた。エマちゃんも編入してきたんだって」
「うん」
じゃあよろしく──と手を愛は差し出した。
「…こちらこそ」
不思議なことにこの年代の女子は、打ち解けるのにさほどの時間を要しない。
数日、経った。
「数学のレポートで分からないところがあるから」
というので、愛が西陣までやって来た。
翔一郎は打ち合わせで河原町御池のホテルに出かけている。
「旦那さんは?」
そう訊いてくる愛に、
「翔くん今日は打ち合わせだよ」
エマは答えた。
「オフィスの机で大丈夫かなぁ?」
「うん」
写真が置いてある、事務所代わりの机でエマと愛は、レポートを片付け始めた。
まごつく愛を尻目にエマは何の渋滞もなく、数式を解いてゆく。
翔一郎がエマを選んだ理由は、こうした回転の早さではなかろうか…と愛はこのとき感じ取ったらしく、
「エマちゃんはさ、どうやって旦那さんと知り合ったの?」
子供じみた質問をぶつけてみた。
「信じるかどうかは分からないけど」
と前置きした上でエマは、翔一郎との馴れ初めをかいつまんで話した。
「まるで映画みたい」
「私なんかは奇跡って呼んでるけどね」
エマが言うと愛の顔がほころんだ。
「ね、愛がいつも首にかけてる、そのカメラなんだけどさ」
そう言えば愛は、首に古い小さなカメラを提げている。
「凄く年期の入ったカメラだけど、もしかしてアンティークとか?」
「これね…おじいちゃんの形見なんだ」
「あっ…愛、ごめん」
「いいって」
愛のアクセントが少し変わった。
「…愛って東京生まれではないよね?」
「うん、東北の方だよ」
「東北かぁ」
まだ行ったことないよ、とエマは答えた。
「私は田舎の方で果物の畑ばっかりだったけど、いいところだよ」
愛は目を細め、遠くを見るように言った。
「ご飯とか美味しそうだよね」
「美味しいよ」
いつか地元の温泉へ一緒に行こう、という話がまとまったころ、翔一郎が帰ってきた。
「今戻ったで」
「あ、おかえりー」
見ると愛がいる。
「ほら、こないだ話した香月愛ちゃん」
「あぁ」
互いに会釈を交わした。
「…お、古いライカやないか」
仕事柄、カメラだけは目につくらしい。
「おじいちゃんの形見なんだって」
「そうか…ほんで、ライカ使いこなせるんか?」
「写し方が分からなくて」
「よっしゃ」
今度ほんなら基本的な使い方だけでも教えたる──と翔一郎は、簡単なレクチャーを約束したのであった。
「良かったね、プロに教えてもらえるんだよ」
いいながら愛が陣内一誠と知り合いなのをエマは思い出したが、
(多分大した知り合いじゃないだろうし)
と、エマはそのまますぐまた忘れてしまうのであった。
いっぽう。
「その前にカメラが動くかどうか見なあかんから」
ちょっと貸してや、と愛のカメラを手に取った。
「少し水かぶっとんな…ただ、中のフィルムは何とかなりそうやな」
いい職人さん知っとるからメンテナンス出しとき、と翔一郎は愛の代わりで修理に出すことにしたのである。
野球なんぞ日頃は興もなさげな女子高校生も、この時期ばかりはどこの何番の選手がカッコいいだの、そんな話題で耳目を集める。
しかも。
この年は翔一郎の母校が久々に出場する、というのがすでに決まっていた。
県立の学校だけにやかましくはなかったが、
──応援団への寄付の依頼について。
という封書が何枚も来ると逆に、
(誰が意地でも出すかい)
というあまのじゃくな感情が、翔一郎は湧いて出るのであった。
数日、過ぎた。
どこからか、高校野球のラジオの中継が聞こえてくる。
時折ザーザーと雑音が混ざって、
(ちゃんとチューナー合わさんかいな)
少しだけイラつく。
が。
ジリジリと蒸し暑い京都の夏には少し鬱陶しいノイズながら、逆にないと困る風物詩でもある。
翔一郎に個展の話が舞い込んだのは、そうした時候であった。
持ち込んだのは、若い女である。
「香月愛」
と書かれたポップな花柄の名刺を差し出したセーラー姿の彼女は、「東京で写真を見た」と言った。
「あ、制服の女の子を撮った写真ですやろ」
あれはいわゆる瓢箪から駒っちゅうやつですのや──と翔一郎は苦笑いを浮かべ、
「ですよって個展やるほどのレベルとちゃいますのや」
と、エマが持ってきた麦茶を飲んだ。
「でもあのあと発表された苔庭の写真、雑誌とか取り上げられてますよ」
あれか、と翔一郎はピンと勘が働いた。
雨上がりの朝早くに嵯峨の鹿王院へ行って撮ってきた一枚のことであろう。
「東京じゃあ中々ああいう写真は撮れないので、やっぱり京都の写真家さんでないとああは行かないよねって、話題になってたんですよ」
「まぁあれ宣伝に使うからって撮っただけの話ですよって、おまけに」
京都は素材の宝庫で、素人でもそこそこ撮れるというような話をしてから、
「それだけにプロがやってゆくにはシビアな目もあるし、逆に言うたら京都のプロの写真家は、うちみたいのは別にしてみんな実力が高い…っちゅう話なんですわぁ」
翔一郎は身も蓋もない言い方をした。
「そうなんですか」
「せやから、しっかりリサーチしてかからんと、前に東京から進出してきた大手の事務所みたいに、失敗して都落ちっちゅうことかてあんのですわ」
「でもそれで成功したら、スゴくないですか?」
「そら成功したら、の話ですわな」
まぁ個展の話は目一杯考えときましょ──というと、香月愛というその謎の女は帰って行った。
「…個展、するの?」
エマが麦茶を下げに来た。
「あー…エマは覚えといた方がえぇから教えとくけど」
考えときましょ、は分かりやすく言うとお断りの合図なのだ…と翔一郎は言い、
「気を遣ってやんわり断るのも、まあ京都式の社交術やな」
十年以上も暮らすと嫌でも身に付くものであるらしかった。
送り火の済んだ頃、一誠に借りていた資料を代わりでエマが返しに行くことになり、自転車で烏丸御池の陣内事務所まで駆ったことがある。
「エマちゃんが来るとは珍しいなあ」
陣内一誠は打ち合わせから戻ったばかりらしく、シュッとしたスーツを着こなしていた。
「饗庭が借りていた資料を返しに来ました」
「わざわざサンキュな」
一誠は受け取った。
「あんまり顔見んけど最近の翔一郎はどや?」
「相変わらずバタバタ走り回ってます」
一誠は吹き出した。
「あいつ、仕事は出来るし手際も悪くはないんやが、少しだけイラチで神経質なとこがあってやな」
そういう生まれ持った中身は変わらんようやな、というと包装に入った八ッ橋をエマに渡した。
「おもろいこととか、なかったんか?」
「面白いかどうかは分からないんですけど」
とエマは、香月愛が西陣に来た話をした。
「あー…あいつか」
「陣内さんの知り合いなんですか?」
「まぁな。悪い子やないんやが、ちょっと色々ある子やからな」
翔一郎に今度話せる機会があったら話しとく、といい、その日は西陣に戻った。
夏休みが明けた最初のスクーリングの日、いつものように自転車で、エマが二条城の堀端にある通信制の高校へ行くと、この日から新しく編入する生徒が来る、というのでソワソワした空気に、教室は変わっていた。
特に男子の生徒が、
「女子らしいけどベッピンなんやろか」
とはしゃいでいる。
(そういえば)
エマが初めてスクーリングに来た日も、男子は騒いでいて担任が怒鳴った記憶がある。
(いつのときも男子って子どもだよね)
エマは少し懐かしかった。
国士舘で剣道をやっていたという、獅子舞の頭のような顔をした担任が教室に入った。
「今日から新しい生徒が加わる」
と獅子頭が言うと、
「…はい」
蚊の鳴くようなか細い声でおずおず引き戸を開けた。
視線を向けると、
「…あ」
驚いた。
無理もない。
先だって個展の話を持ち込んできた香月愛なのである。
だが。
愛は気づかない。
(気づかない方がいい場合もある)
少し伏し目がちのエマはそのまま、遣り過ごそうとした。
しかし。
愛が何かに気づいた様子で、
「あっ」
と声をあげた。
エマが視線を上げると、
「饗庭お前、香月と知り合いか?」
担任が訊いてきた。
エマがいや、あの…と口ごもると、
「まあ詳しくは知らんけど、知らん訳でもないようやから…香月、饗庭の隣に座れや」
「はい」
愛はエマの隣に座った。
「ほな教科書、三十五ページ開きや」
カリキュラムはさりげなく始まったのであった。
放課後。
エマが帰り支度を始めていると、
「エマちゃん」
素敵なお兄さんね──と愛は声をかけてきた。
「あれは兄じゃないの」
主人なの、とエマが言うと愛はさすがに驚いた様相になったが、
「まるでドラマみたいな夫婦だね、女子高生の奥さんなんて」
「そうだよね」
でも羨ましいな──と愛は呟いた。
「?」
「先生にさっき聞いた。エマちゃんも編入してきたんだって」
「うん」
じゃあよろしく──と手を愛は差し出した。
「…こちらこそ」
不思議なことにこの年代の女子は、打ち解けるのにさほどの時間を要しない。
数日、経った。
「数学のレポートで分からないところがあるから」
というので、愛が西陣までやって来た。
翔一郎は打ち合わせで河原町御池のホテルに出かけている。
「旦那さんは?」
そう訊いてくる愛に、
「翔くん今日は打ち合わせだよ」
エマは答えた。
「オフィスの机で大丈夫かなぁ?」
「うん」
写真が置いてある、事務所代わりの机でエマと愛は、レポートを片付け始めた。
まごつく愛を尻目にエマは何の渋滞もなく、数式を解いてゆく。
翔一郎がエマを選んだ理由は、こうした回転の早さではなかろうか…と愛はこのとき感じ取ったらしく、
「エマちゃんはさ、どうやって旦那さんと知り合ったの?」
子供じみた質問をぶつけてみた。
「信じるかどうかは分からないけど」
と前置きした上でエマは、翔一郎との馴れ初めをかいつまんで話した。
「まるで映画みたい」
「私なんかは奇跡って呼んでるけどね」
エマが言うと愛の顔がほころんだ。
「ね、愛がいつも首にかけてる、そのカメラなんだけどさ」
そう言えば愛は、首に古い小さなカメラを提げている。
「凄く年期の入ったカメラだけど、もしかしてアンティークとか?」
「これね…おじいちゃんの形見なんだ」
「あっ…愛、ごめん」
「いいって」
愛のアクセントが少し変わった。
「…愛って東京生まれではないよね?」
「うん、東北の方だよ」
「東北かぁ」
まだ行ったことないよ、とエマは答えた。
「私は田舎の方で果物の畑ばっかりだったけど、いいところだよ」
愛は目を細め、遠くを見るように言った。
「ご飯とか美味しそうだよね」
「美味しいよ」
いつか地元の温泉へ一緒に行こう、という話がまとまったころ、翔一郎が帰ってきた。
「今戻ったで」
「あ、おかえりー」
見ると愛がいる。
「ほら、こないだ話した香月愛ちゃん」
「あぁ」
互いに会釈を交わした。
「…お、古いライカやないか」
仕事柄、カメラだけは目につくらしい。
「おじいちゃんの形見なんだって」
「そうか…ほんで、ライカ使いこなせるんか?」
「写し方が分からなくて」
「よっしゃ」
今度ほんなら基本的な使い方だけでも教えたる──と翔一郎は、簡単なレクチャーを約束したのであった。
「良かったね、プロに教えてもらえるんだよ」
いいながら愛が陣内一誠と知り合いなのをエマは思い出したが、
(多分大した知り合いじゃないだろうし)
と、エマはそのまますぐまた忘れてしまうのであった。
いっぽう。
「その前にカメラが動くかどうか見なあかんから」
ちょっと貸してや、と愛のカメラを手に取った。
「少し水かぶっとんな…ただ、中のフィルムは何とかなりそうやな」
いい職人さん知っとるからメンテナンス出しとき、と翔一郎は愛の代わりで修理に出すことにしたのである。