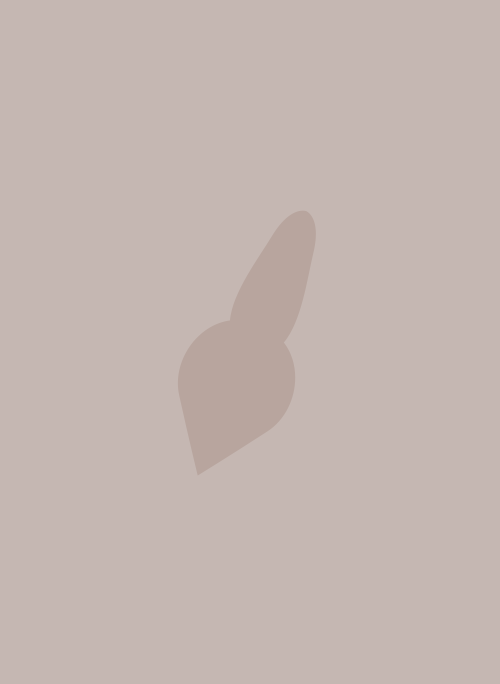(代々木健介)
「理由は単純だ。君がプロレスラーだからだよ」
親父の言葉を聞いて、南斗さんは顔を青くした。
「なんだよそれ?説明になってねえぞ!」
おれは怒鳴った。
親父は静かにおれを見据えた。
「わからないのか?健介」
「わからねえな。プロレスラーの何が悪いっていうんだ?」
「プロレスラーが、悪いとは言わん。しかし、おまえの相手をさせるわけにはいかんのだ」
「……どういうことだ?」
親父は、南斗さんを横目で見ながら言った。
「プロレスというものはな、偽物の固まりなんだ」吐き捨てるような口調だった。「鍛えた筋肉も見せかけだけの偽物。戦う理由も偽物。戦い自体も偽物。そして技も偽物。……健介、今日山へ入る前に、この少女から何度かプロレスの技を受けていたな。……愚かなことしおって。おまえには、小さい頃から、真の空手を、本物の戦いの術を教えてきたのだ。あんな偽物の技に触れていたら、空手の感性が鈍ってしまうではないか」
親父は、修行の相手にプロレスラーである南斗さんはふさわしくないと言いたいわけだ。
「……ごめんなさい」
南斗さんが頭をさげた。歯を喰いしばっていた。
「南斗さんがあやまる必要はねえよ」
おれは強く言った。
親父の言いたいことも分かる。確かに、プロレスというものには、作りものの要素が含まれているのだろう。
しかし、南斗さんは違うと思った。
技を喰らったおれには分かる。彼女の持つ技術は、例え作りものであろうとも、決して偽物ではない。
なんというか、決して楽して身につけたものではないと分かるのだ。
そのとき、アトミック南斗が、親父の背後にぬっと立った。大きな影が、親父の全身を覆った。
「おうおうおう、黙って聞いてりゃあ、ずいぶんとプロレスを馬鹿にしてくれるじゃねえか」
「理由は単純だ。君がプロレスラーだからだよ」
親父の言葉を聞いて、南斗さんは顔を青くした。
「なんだよそれ?説明になってねえぞ!」
おれは怒鳴った。
親父は静かにおれを見据えた。
「わからないのか?健介」
「わからねえな。プロレスラーの何が悪いっていうんだ?」
「プロレスラーが、悪いとは言わん。しかし、おまえの相手をさせるわけにはいかんのだ」
「……どういうことだ?」
親父は、南斗さんを横目で見ながら言った。
「プロレスというものはな、偽物の固まりなんだ」吐き捨てるような口調だった。「鍛えた筋肉も見せかけだけの偽物。戦う理由も偽物。戦い自体も偽物。そして技も偽物。……健介、今日山へ入る前に、この少女から何度かプロレスの技を受けていたな。……愚かなことしおって。おまえには、小さい頃から、真の空手を、本物の戦いの術を教えてきたのだ。あんな偽物の技に触れていたら、空手の感性が鈍ってしまうではないか」
親父は、修行の相手にプロレスラーである南斗さんはふさわしくないと言いたいわけだ。
「……ごめんなさい」
南斗さんが頭をさげた。歯を喰いしばっていた。
「南斗さんがあやまる必要はねえよ」
おれは強く言った。
親父の言いたいことも分かる。確かに、プロレスというものには、作りものの要素が含まれているのだろう。
しかし、南斗さんは違うと思った。
技を喰らったおれには分かる。彼女の持つ技術は、例え作りものであろうとも、決して偽物ではない。
なんというか、決して楽して身につけたものではないと分かるのだ。
そのとき、アトミック南斗が、親父の背後にぬっと立った。大きな影が、親父の全身を覆った。
「おうおうおう、黙って聞いてりゃあ、ずいぶんとプロレスを馬鹿にしてくれるじゃねえか」