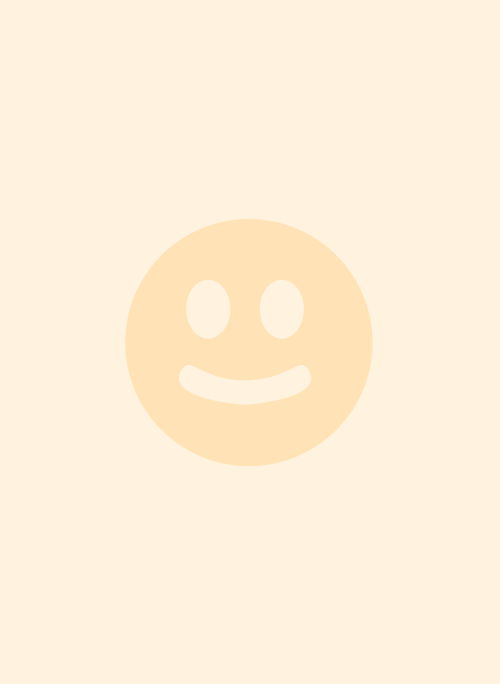*
江戸っ子は銭湯好き、と云われるだけある。
混浴であるにも関わらず、男女子供がみな同じ湯船に浸かって、ふう、と和んでいた。
「枝がつかえまさあ」
「田舎者でござい」
狭い浴槽の中は、まさに芋の子と親を一緒に洗ったようである。
湯に入ればどうしても人の手足に指先が当たってしまうので、こうやって一声かけてから湯船につかるのが、先頭の常識であり礼儀だ。
そんな窮屈な湯船に入る前に、菊之助は流し場でひたすら体に湯をかけ、百合を待っていた。
人目を憚るように肩を狭めて、だ。
なにしろ、銭湯は混浴。
しかも豪胆な女どもは体つきの良い男を見ては、きゃあきゃあとはやし立てるのだ。
細身でしなやかな身体を布で隠し、菊之助は女に気を配るばかりだった。
「姉ちゃんよう、そんなに湯屋を楽しみにしてたのか?」
正直な所、湯船につかるのは温かくてよいが、へちまの実で体の汚れを落とす作業のどこが楽しいのか、菊之助には理解しかねる。
「え?なんだって?」
流し場で幾度も体を洗っていた百合は、朧げな菊之助の声に、百合はいまいちど耳を傾けるのだった。
「だから、どうしてそんなにも体を洗う必要があるんだい」
「そりゃあ、汚れを落として綺麗にするためさ。
女ならそれくらいしないと」
「俺あ、あったまるだけで充分だよ」
菊之助はたおやかな身体を縮めて、体を流した百合と共に柘榴口をくぐった。
ここをくぐれば、すぐ前に浴槽がある。
「田舎者でござい」
言うや、菊之助は急いで首から下を湯船に沈めた。
百合も湯に浸って、やっと一息つく。
「蓮兵衛んとこのおばさんが大根を半分くれたから、味噌でもつけて食べようか」
百合が瞼を伏せる。
今はもう暮れ六つで、ちょうど晩飯時である。
「ああ、いいなあ大根。
味噌つけて食べようぜ」
菊之助の食欲は早くも、長屋に帰って大根を炊きたいと要求している。
子供侍の顔は嘘が不得手なだけあって、恍惚に涎を垂らさんばかりである。
「もう、子供なんだから」
くくっ、と歯を出して頬を緩め、百合は菊之助の頭を雑になでる。
菊之助はその仕草に、つい安堵へと誘われそうになった。
不満の意を表すのを忘れて、だ。