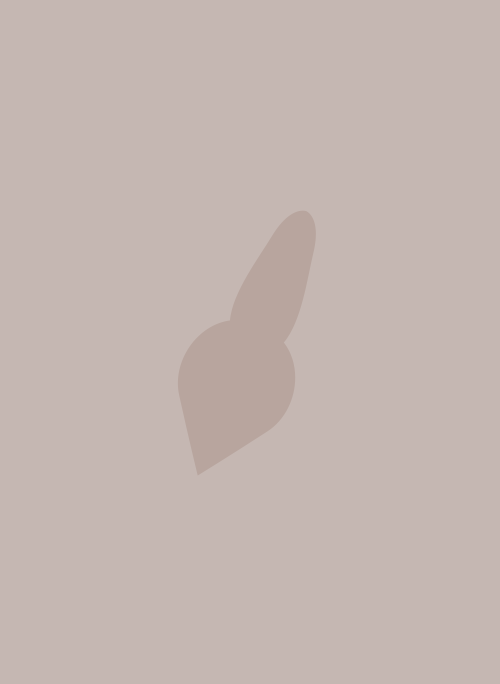娘が死んで、気が狂った芸術家がいた。
彼の名は座木周一郎。七十二歳。絵画と造形の分野で、昭和の時代に大いに活躍し、富と名声を築きあげた高名な芸術家である。狂気を感じるほどの精密さで作られる彼の絵画や造形作品は、見るものの魂を引きずりこむかのような迫力に満ちていた。裏社会を仕切る財閥系の人間たちが、皆、周一郎の作品の愛好家となった。
長い間、彼は孤独の身の上であった。気難しい性格が災いして、家族はひとりもいなかった。
若い頃は、作品製作に夢中になっていたので、そのことを苦に感じることはなかったのだが、齢六十を過ぎる頃になると、広い屋敷での老人の一人暮らしがだんだんとさみしくなってきた。
そして十年前、周一郎は孤児院から、ひとりの少女を養子としてひきとった。
少女の名前は、遊美。
ひきとった当時は、まだ七歳であった。
素直で活発な女の子だった。
周一郎の肩書きや、厳格な雰囲気に気圧されず、初めて会ったときから、堂々と甘えてきてくれた。周一郎は、そんな遊美を大事にかわいがって育ててきた。ずっと誰の前でもしかめっ面ばかりしていた周一郎だが、遊美といっしょにいるときだけは、温厚な笑顔を見せていた。
十年後、六月の梅雨時に、その遊美が死んでしまった。
バスの交通事故に巻きこまれてしまったのだ。