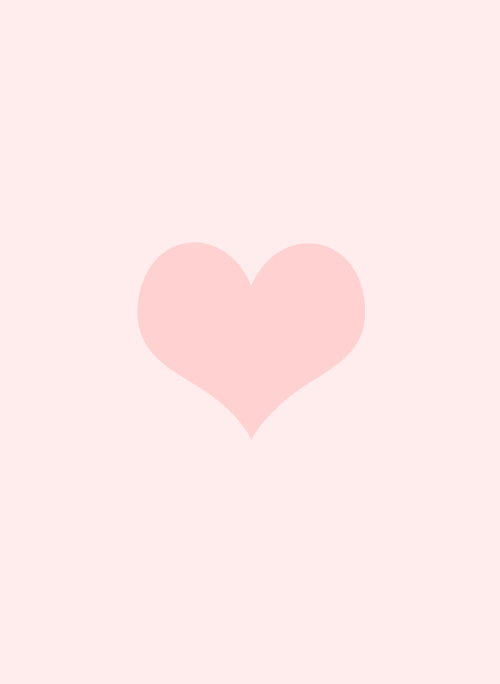ついさっきまでソファに座ってテレビを見ていたはずなのに、いつの間にか眠ってしまっていたらしい。
額に軽い痛みが走り、ふと目を開くと、ぼやけた視界の中に見慣れた顔が映った。
「……あ、おかえり」
「ただいま。……つーかお前、来るならメールくらいしろよ」
そしたらもう少し早く仕事切り上げたのに。
そう言ってネクタイを緩める彼の手元を、起きぬけの意識の中でぼんやりと見つめる。
大人の男の人が気怠そうにネクタイを解く仕草って、なんか格好いい。
だから、いつも年上の人を好きになるのかもしれない。
10も離れている、この人のことを。
「飯食ったの?」
「さっきお菓子食べた。こっちに置いてたやつ」
「あっそ。で、今日も泊まりに来たのか」
「うん、……今うち、お客さん来てて、」
「わかってるよ」
お客さん。――そう言えば、彼には全て伝わる。
私の母親は男遊びが好きで、二人で住んでいる狭いアパートにすぐ見知らぬ男の人を連れてくることを。
どう考えても邪魔な私は、その男の人が帰るまで外で暇を潰していなければならないことを。
彼は全て知っている。
皮肉にも、私たちの出会いもまた、母親を通したものであったからだ。