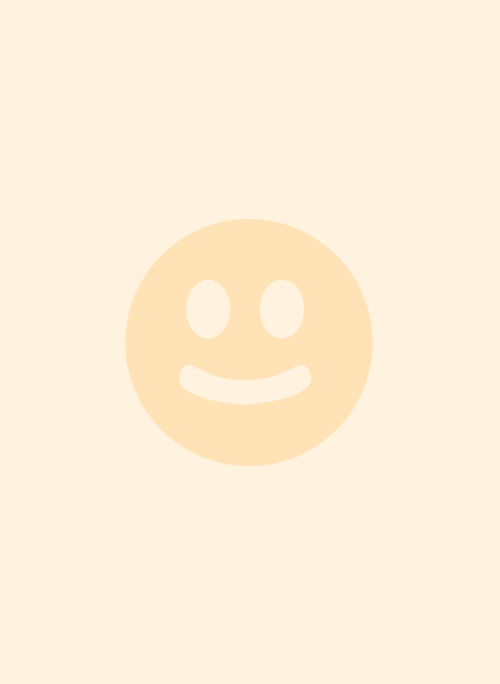「あ……」
晴也を見て、女子生徒、鈴木はふと表情を和らげる。いや、それでもひどく青ざめた面であった。
「知り合いか?晴也」
「同じクラスの子です」
吉郎は忙しなく顎に触れ、鈴木に一瞥をくれる。
「あの、あの……」
吉郎が晴也の知人と聞いてほんの少しばかり安堵したのか、鈴木は次第に血の気を取り戻していった。
「先生を探してたら、こっ、ここで声がして、来てみたら、ばっ、化け物が」
それでも口調はしどろもどろで、さきほど彼女の身に起こった怪異の恐ろしさの度合いを物語っている。
吉郎は心ここに非ずとばかりの瞳で鈴木を見つめている。
鈴木はごくりと固唾を飲む。やはり吉郎の不良顔負けの鋭敏な容姿に気後れしたのだろう。
「うう」
憔悴しているのか、鈴木は弱々しくのろい動きで身体をのけぞらせる。
「あの、鈴木さん。まずは落ち着いてください。とりあえず教卓から出て」
花子が事件現場に居合わせて気が動転した者をなだめる警察官のような口ぶりで対応する。
すっかり縮こまって、鈴木はすがりつかんばかりに視線を花子に向ける。
先ほどからそうだったが、鈴木はあまり晴也に目を向けていない。
ただ吉郎と花子を見るたびに、幾度か怯えるようなそぶりをするだけである。
鈴木は日直日誌を握りしめていた。
「先輩、あの子、化け物って言ってましたけど、霊でしょうかね」
「霊と人と、自然の数だけ妖がおる。
まさに、いい具合に人がおって森も山も川もあるこの県は、妖のええ住処や。
そこらへんの霊魂を喰いに学校に出没することも、少なくあらへんけど……」
「ですよね。妖だって、人間が自分たちを視たらどうなるかなんて、判断できるはずですし。
人を驚かすだけならよくありますけど、妙な霊気が……」
霊的関係者の彼らは、晴也にでも聞き取れる声量で、肩を寄せ合って話す。
俗にいう、ひそひそ話になっていない。