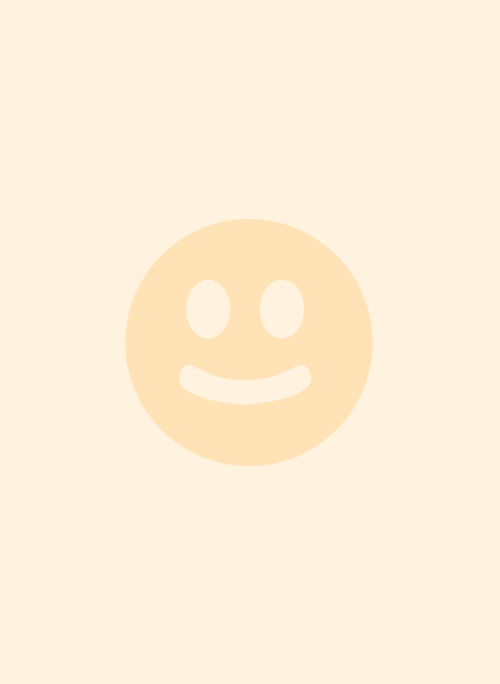(しまった‼)
早く。一秒でも早くこの場から逃れなくてはならない。闘争本能ならぬ逃走本能が、ひいひいと悲鳴を上げる。
しかし、もちろんのこと、こんな状況で逃げ切れるはずもない。
吉郎は長身を生かした走りをし、渡り廊下の戸を開け、電光石火の速さでこちらまでやってきた。
そんな吉郎に、晴也はあえなく捕獲されたのだった。
「もう、つれへんやん。
なんで逃げんの?一日にして早くも俺の事嫌いになったん?」
強引に腕を組まれ、渡り廊下の中央まで連行される。
もはや袋の鼠ならぬ、猫に咥えられた鼠である。成すすべをなくした晴也は、最後の頼みとばかりに、視線であの女子の陣に助けを求めた。
求めたが、彼女らはもうホモ疑惑のある吉郎に幻滅して、退散してしまっている。
「おやっ、あなたは秀才眼鏡君!」
晴也を迎えた花子は、とろけるような笑顔になった。
―――彼女の本性を知らなければ、惚れているところである。
だが、晴也は知ってしまっていた。
駆け寄ってきた花子が、げっそりとしてうつむいている晴也の面を覗き込んだ。
そして案の定、こう問うてきた。
「あれっ。眼鏡君、愛しのバレー部の準エース君はどうしたんですか?」
「細川ならとっくに部活ですよ……」
すっかり生気の失せた、消え入らんばかりの声で晴也が答える。
花子はさも残念そうに肩を落とした。
「そうですか。ああ、運動部とは酷なもんですね。愛しい人と放課後に話す暇も与えないだなんて」
細川が聞いたら、ホモのホの字もなく卒倒するに違いない。
いったい、花子の目はこの世の男たちをどういうふうに見ているのか。
ほとんど困惑した晴也は本気で、花子の視点から男子を視てみたくなった。