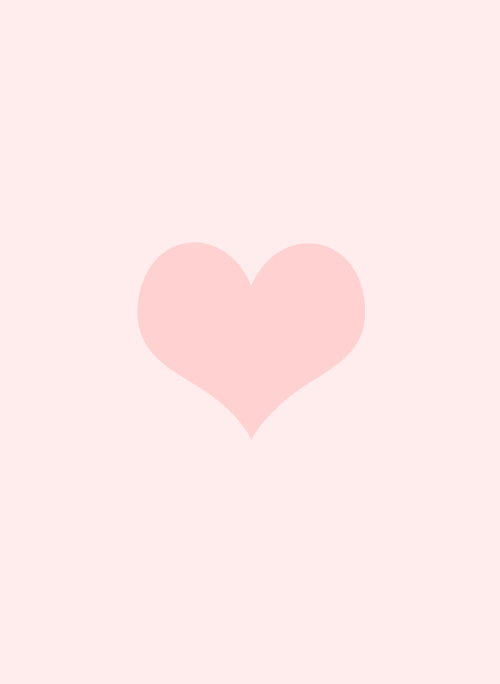(お父さんがこの人、というかこのアンドロイドを呼び出した?)
ナナは一瞬考えてから、タカをキッと睨んだ。
「嘘つき! 父がそんな事するはずない」
「ほお、どうして?」
「出来たはずない、と言うべきね。だって、父は心臓の発作であっという間に死んじゃったのよ? とてもそんな暇はなかったわ」
ナナは、自分の目の前で倒れ込んだ父親を思い出し、何も出来なかった自分が歯痒く、悲しくなった。
「ああ、その事か。僕は地球の何処にいても、絶えず天馬博士の心臓が発する鼓動をキャッチしていたんだ。そしてもしその鼓動が途絶えたら、任務を投げ出してでもこの屋敷に来るようプログラムされていたんだよ」
ナナはタカの説明をすんなりと受け入れた。普通なら信じ難い話であったが、タカがアンドロイドである事自体が信じ難い話であり、もはや少々の事では驚かなくなっているナナであった。
だが、新たな疑問がナナの中で生じた。
ナナは一瞬考えてから、タカをキッと睨んだ。
「嘘つき! 父がそんな事するはずない」
「ほお、どうして?」
「出来たはずない、と言うべきね。だって、父は心臓の発作であっという間に死んじゃったのよ? とてもそんな暇はなかったわ」
ナナは、自分の目の前で倒れ込んだ父親を思い出し、何も出来なかった自分が歯痒く、悲しくなった。
「ああ、その事か。僕は地球の何処にいても、絶えず天馬博士の心臓が発する鼓動をキャッチしていたんだ。そしてもしその鼓動が途絶えたら、任務を投げ出してでもこの屋敷に来るようプログラムされていたんだよ」
ナナはタカの説明をすんなりと受け入れた。普通なら信じ難い話であったが、タカがアンドロイドである事自体が信じ難い話であり、もはや少々の事では驚かなくなっているナナであった。
だが、新たな疑問がナナの中で生じた。