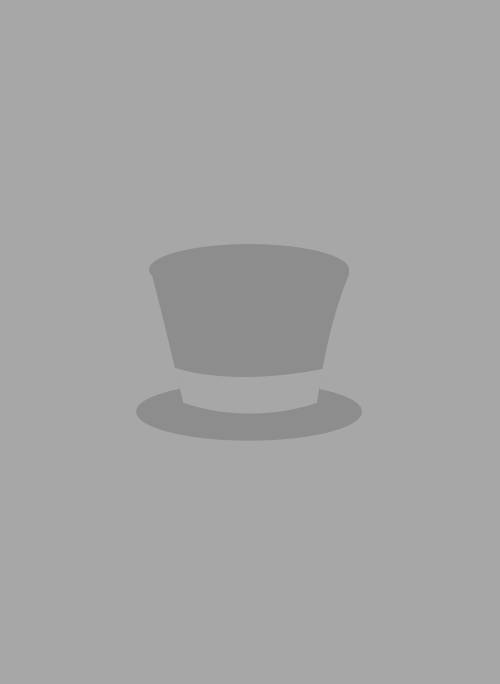それから三日経った日の夜。仕事からアパートの前まで帰宅した私は自分の目を疑った。間違いで無ければ今、確かに階下のドアが閉まったのだ。
あれから浅村も姿を現しては居ない。という事は、違う方向に捜査が転換し、階下の目撃証言も今ではもう必要性が無くなった。だから、ひっそりと帰って来たのか、あるいはすぐに引っ越しをする手筈にでもなっているのかも知れない。そうなると、何故に私を仕立て上げようとしたのかを聞かないと気が収まらないというものだ。
私は小走りに階下のドアの前に立つと右手の指でインターホンを押そうとした。
「いや、駄目だ。録画される」
指はインターホンのボタンに触れる直前でその動きを止め、私は浅はかな行動を取ろうとした自分を戒めた。
向こうから出て来るのを待つ。そして、適当な所で話かける。
そうだ、そうしよう。きっとそれが最善の策だ。人目が気にならない場所に身を沈めると、ドアが開くのをじっと待った。
ところがドアは意外にも早く開き、徹夜さえ覚悟していた私の気負いはさり気なくもどこか腰を折られた格好となった。
腕時計に目をやる。夜光塗料が塗られた針は緑色の明るい細かな光で10時過ぎを指している。
少し早いが、やっぱり夜逃げか。
アパートの薄暗い街灯は、中肉中背の男の姿を闇夜に浮かび上がらせた。
「こいつか」
何の恐ろしさも無い余りにも普通の中年の男。緊張感が一瞬にして消え去る。男はアパートの裏の駐車場に向かう階段を降りた。
私は、さり気なく身を隠しながら跡を追う。男は、周囲に気配りをする素振りも見せずに駐車場の中に入って行った。
「マズイ」
ここで走り去られては何も得られない。私は、男が車に乗った瞬間に助手席に飛び込んだ。咄嗟の行動だった。男の顔を見る。消えようとするルームランプの中に口と眼を開けたままの表情が止まっていた。
「出しなさい」
私は強い口調で命令した。男は、ガクガクと何度か頷くと一心不乱に車を発進させた。
「あの・・・・何処に?」
男の恐る恐るの言葉が何故かムカついた。
「何処でもいい。とにかく走らせて」
あれから浅村も姿を現しては居ない。という事は、違う方向に捜査が転換し、階下の目撃証言も今ではもう必要性が無くなった。だから、ひっそりと帰って来たのか、あるいはすぐに引っ越しをする手筈にでもなっているのかも知れない。そうなると、何故に私を仕立て上げようとしたのかを聞かないと気が収まらないというものだ。
私は小走りに階下のドアの前に立つと右手の指でインターホンを押そうとした。
「いや、駄目だ。録画される」
指はインターホンのボタンに触れる直前でその動きを止め、私は浅はかな行動を取ろうとした自分を戒めた。
向こうから出て来るのを待つ。そして、適当な所で話かける。
そうだ、そうしよう。きっとそれが最善の策だ。人目が気にならない場所に身を沈めると、ドアが開くのをじっと待った。
ところがドアは意外にも早く開き、徹夜さえ覚悟していた私の気負いはさり気なくもどこか腰を折られた格好となった。
腕時計に目をやる。夜光塗料が塗られた針は緑色の明るい細かな光で10時過ぎを指している。
少し早いが、やっぱり夜逃げか。
アパートの薄暗い街灯は、中肉中背の男の姿を闇夜に浮かび上がらせた。
「こいつか」
何の恐ろしさも無い余りにも普通の中年の男。緊張感が一瞬にして消え去る。男はアパートの裏の駐車場に向かう階段を降りた。
私は、さり気なく身を隠しながら跡を追う。男は、周囲に気配りをする素振りも見せずに駐車場の中に入って行った。
「マズイ」
ここで走り去られては何も得られない。私は、男が車に乗った瞬間に助手席に飛び込んだ。咄嗟の行動だった。男の顔を見る。消えようとするルームランプの中に口と眼を開けたままの表情が止まっていた。
「出しなさい」
私は強い口調で命令した。男は、ガクガクと何度か頷くと一心不乱に車を発進させた。
「あの・・・・何処に?」
男の恐る恐るの言葉が何故かムカついた。
「何処でもいい。とにかく走らせて」