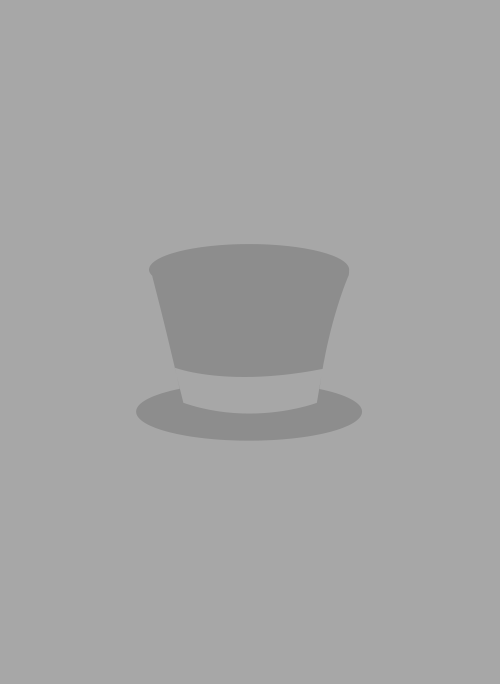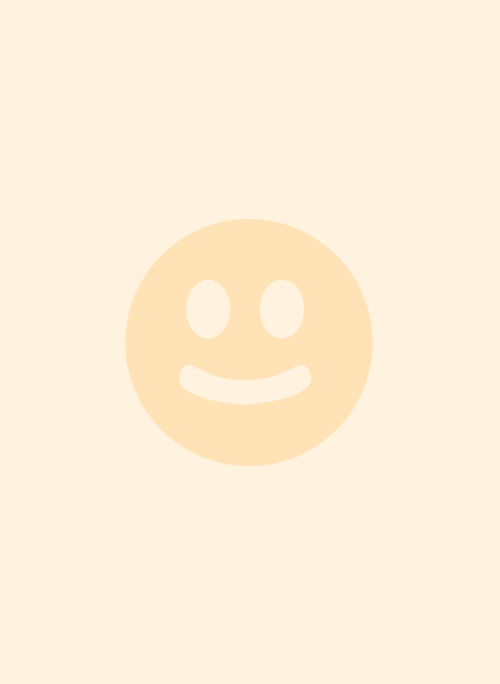津高祭は無事幕を閉じた。
片付けを済ますと、俺はその足で図書館へと向かう。
「やっぱりいた」
ソファーに座っている高津はこちらを向いた。
「お疲れ様」
「お疲れ」
「よかったよ」
「そりゃどうも」
一言ごとの言葉のキャッチボールはすぐに終わってしまう。
外の景色を見ながら、俺は一文は完成させようと口を開いた。
「俺が書道を始めたのは小学三年からだった。理由はたいしたこと無い。・・・好きな子が習っていたからだ」
「よくあることで」
「続けていたらそのうちその子を超えちまったみたいでな。いざ告白したときには、自分より字の上手い男は嫌だ。と、フられた。でも、それでやめようとは思わなかった。通い続けた」
「それで今に至るってわけね」
高津は一度、お疲れ様と言ってから俺を見ようとしない。ずっと本を読んでいる。
俺はそれが腹立たしく思えた。
「ありがとう」
「・・・・キモ」
よし。こっちを向いた。
「うわっ。可愛くねー」
「余計なお世話」
高津は少し不機嫌そうに口を曲げると、それで?と。
「スランプは抜けた?」
「おう」
お蔭様でな。
そう言いながら、高津の隣に座った。
「それで。高津に言おうと思ったことがあるんだ」
「ぜひ、聞きたいね」
「俺。この先も書道続けていこうと思うんだ」
「つまり?」
「書道家になる」
おぉ。と、感心した反応を見せる。
「そりゃまた大きく出たことで」
「練習あるのみだがな」
「それじゃあ。有名になったらその作品をただで貰おうかな」
「それを売るんだろ?」
「バレた?」
全く、恐ろしい女だ。
肩をすくめた。
「実はね。私にも出来たんだー。夢」
「ほう。それは聞きたいな」
すると、高津は立ち上がった。そして楽しそうに笑った。
「小説家」
片付けを済ますと、俺はその足で図書館へと向かう。
「やっぱりいた」
ソファーに座っている高津はこちらを向いた。
「お疲れ様」
「お疲れ」
「よかったよ」
「そりゃどうも」
一言ごとの言葉のキャッチボールはすぐに終わってしまう。
外の景色を見ながら、俺は一文は完成させようと口を開いた。
「俺が書道を始めたのは小学三年からだった。理由はたいしたこと無い。・・・好きな子が習っていたからだ」
「よくあることで」
「続けていたらそのうちその子を超えちまったみたいでな。いざ告白したときには、自分より字の上手い男は嫌だ。と、フられた。でも、それでやめようとは思わなかった。通い続けた」
「それで今に至るってわけね」
高津は一度、お疲れ様と言ってから俺を見ようとしない。ずっと本を読んでいる。
俺はそれが腹立たしく思えた。
「ありがとう」
「・・・・キモ」
よし。こっちを向いた。
「うわっ。可愛くねー」
「余計なお世話」
高津は少し不機嫌そうに口を曲げると、それで?と。
「スランプは抜けた?」
「おう」
お蔭様でな。
そう言いながら、高津の隣に座った。
「それで。高津に言おうと思ったことがあるんだ」
「ぜひ、聞きたいね」
「俺。この先も書道続けていこうと思うんだ」
「つまり?」
「書道家になる」
おぉ。と、感心した反応を見せる。
「そりゃまた大きく出たことで」
「練習あるのみだがな」
「それじゃあ。有名になったらその作品をただで貰おうかな」
「それを売るんだろ?」
「バレた?」
全く、恐ろしい女だ。
肩をすくめた。
「実はね。私にも出来たんだー。夢」
「ほう。それは聞きたいな」
すると、高津は立ち上がった。そして楽しそうに笑った。
「小説家」