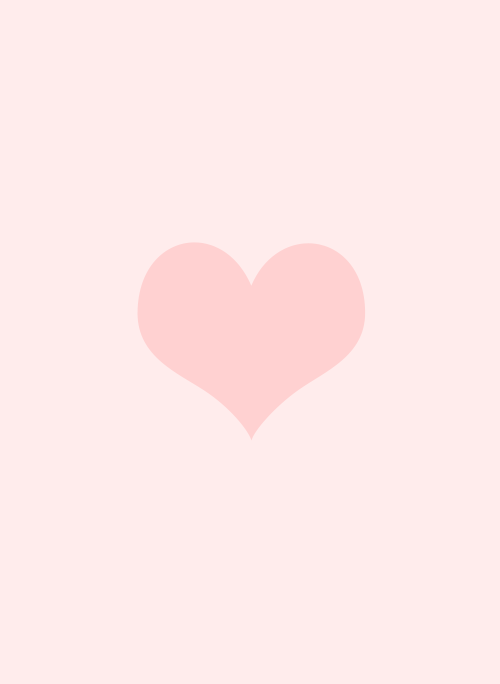「復讐は罪と思いますか」
問われて、暫くの沈黙を守ると彼は否と応えた。
「あなたならそう仰ると思っていました」
質問者は悲しそうに笑った。
その人は右手に赤い水滴のついたナイフを携え、その足元にはうつ伏せに死した人間がある。
赤い絨毯はその滴りでさらに赤く染まり、溜まりは広がり続ける一方でその人の足を汚している。
身に纏ったフロックコートにも、頭に被った帽子にも、僅かに見える指先にまでも飛び散ったそれは、何故だか薔薇の花弁に見えて。
そんな人を眺めながら、紅い両眼の青年はまるで平然と落ち着いている。
「では殺人は罪と思いますか」
「ああ」
「じゃあ、わたしは罪人ですね」
「自覚があるなら、死のうとするな」
からんと乾いた音をたててナイフが溜まりに堕ちた。
言葉が重く突き刺さる。
まるで、嗚呼、死神の鎌のよう。