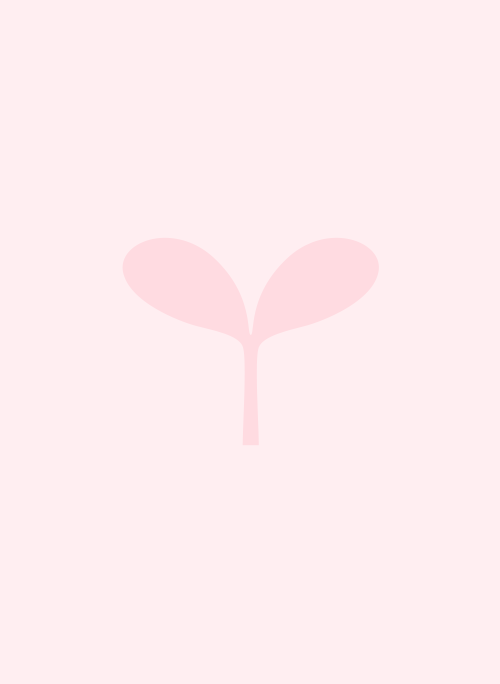―――黒き流れをたずさえし王家の者よ その紋章を我に捧げよ
さすれば懐かしき故郷への道が 開かれる―――
「…って、書いてあるわね…」
「ええ〜っ、じゃあ、その紋章ってのがないとはいれないのか?」
「そういうことね。残念ながら。」
「ちぇ〜っ、せっかくお宝の匂いがしたと思ったんだけどなぁ〜……」
石碑に刻まれた文字を読んで聞かせるニーナの言葉にリュートは大きくため息をつくと、ごろんとその場に横になった。
空には掴めそうなモコモコ雲が浮かんでいた。
ニーナは肩までの色素の薄い髪を2つに結んでいた。
木々の繁った森の中だというのに寒くないのか、キャミソールにショートパンツという軽装。
リュートも同じく軽装ではあるが、小綺麗にしているニーナとは違い、ジーンズもシャツもボロボロだ。
髪も自分で適当に切ったのが手にとるように解る。
バンダナを巻いているのがせめてもの救いだ。
空はとてもよく晴れていて雲一つない青空だ。
木々が作る木陰が心地よい空気を作り、目をつむればすぐさま眠りに落ちること間違いなしだ。
ここは海のど真ん中な名もない小さな島。
白い砂浜に囲まれているが、その中心は木々が密集し、遠くから見るとマリモが白い浮き輪をつけて海に浮かんでいるかのようながいけんだ。
この島が、図書館で見つけた本に載っていた島でありどんな宝があるのかとワクワクして訪れたのだが、あっけなく出鼻をくじかれたのだった。
さすれば懐かしき故郷への道が 開かれる―――
「…って、書いてあるわね…」
「ええ〜っ、じゃあ、その紋章ってのがないとはいれないのか?」
「そういうことね。残念ながら。」
「ちぇ〜っ、せっかくお宝の匂いがしたと思ったんだけどなぁ〜……」
石碑に刻まれた文字を読んで聞かせるニーナの言葉にリュートは大きくため息をつくと、ごろんとその場に横になった。
空には掴めそうなモコモコ雲が浮かんでいた。
ニーナは肩までの色素の薄い髪を2つに結んでいた。
木々の繁った森の中だというのに寒くないのか、キャミソールにショートパンツという軽装。
リュートも同じく軽装ではあるが、小綺麗にしているニーナとは違い、ジーンズもシャツもボロボロだ。
髪も自分で適当に切ったのが手にとるように解る。
バンダナを巻いているのがせめてもの救いだ。
空はとてもよく晴れていて雲一つない青空だ。
木々が作る木陰が心地よい空気を作り、目をつむればすぐさま眠りに落ちること間違いなしだ。
ここは海のど真ん中な名もない小さな島。
白い砂浜に囲まれているが、その中心は木々が密集し、遠くから見るとマリモが白い浮き輪をつけて海に浮かんでいるかのようながいけんだ。
この島が、図書館で見つけた本に載っていた島でありどんな宝があるのかとワクワクして訪れたのだが、あっけなく出鼻をくじかれたのだった。