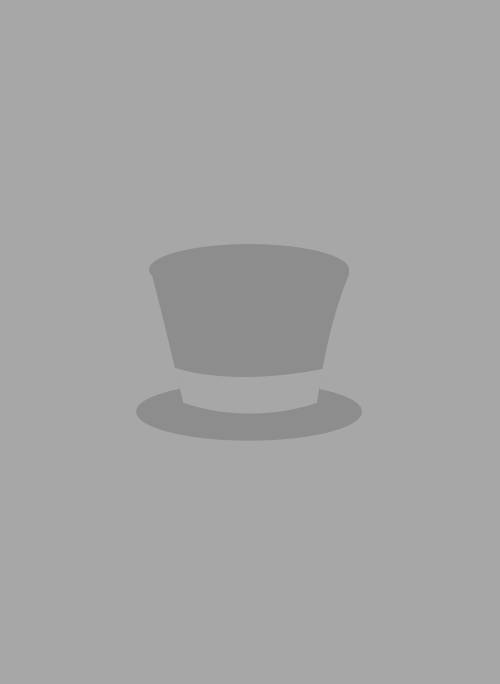「そうだね…」
彼女は、悲しく微笑んだ。
それに、僕は反応するすべを知らなかった。
彼女の笑い…彼女の思い…同情をひくように、彼女が笑いかけても、それに対して、どう反応したらいいのか。
なぜなら、彼女の微笑みは僕に対してではない。どんな答え…慰め、やさしさも、彼女の求めるものじゃない。
「何黙ってるのよ…赤星浩一……」
彼女は、僕を見、少し気まずそうに、下を向き、
「あんたが、話してくれないと……どうして、いいかわからないじゃない」
彼女の言葉は、もっともだが、慰めることも、やさしくするようなことも、僕の口からは、出なかった。
「赤星って…昔からそうだよね」
彼女は笑い、
「なんか……冷たい…。でも、それなのに…いつも、なんかこういうときは、そばにいて……」
彼女は、僕から視線を外すと、
「ずるいよ…」
その場から、駆け出した彼女を僕は、追い掛けることはできなかった。
(昔からか……)
彼女が去った屋上で、僕は1人…空を見上げた。
澄んだ青空に、やけに眩しい太陽。
「そんな資格は、ないよ」
そう…僕には、そんな資格はなかった。
彼女は、悲しく微笑んだ。
それに、僕は反応するすべを知らなかった。
彼女の笑い…彼女の思い…同情をひくように、彼女が笑いかけても、それに対して、どう反応したらいいのか。
なぜなら、彼女の微笑みは僕に対してではない。どんな答え…慰め、やさしさも、彼女の求めるものじゃない。
「何黙ってるのよ…赤星浩一……」
彼女は、僕を見、少し気まずそうに、下を向き、
「あんたが、話してくれないと……どうして、いいかわからないじゃない」
彼女の言葉は、もっともだが、慰めることも、やさしくするようなことも、僕の口からは、出なかった。
「赤星って…昔からそうだよね」
彼女は笑い、
「なんか……冷たい…。でも、それなのに…いつも、なんかこういうときは、そばにいて……」
彼女は、僕から視線を外すと、
「ずるいよ…」
その場から、駆け出した彼女を僕は、追い掛けることはできなかった。
(昔からか……)
彼女が去った屋上で、僕は1人…空を見上げた。
澄んだ青空に、やけに眩しい太陽。
「そんな資格は、ないよ」
そう…僕には、そんな資格はなかった。