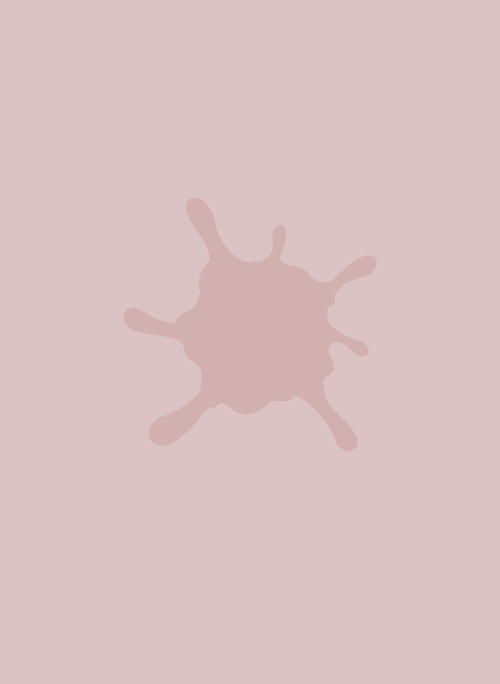-
目を開けるとそこは知らない場所だった。
なんて思う筈もなく、目覚めた瞬間からここが何処で、自分は何をしているのか分かっていた。
頭は変に覚醒していたのだ。
大方僕は気を失っていたのだろう。残っているのは胸を焼くような気持ち悪さと今も尚残る微かな臭さ。
それに咳を溢した後に立ち上がった。
見たところ何処かの部屋の一室であろうが、何せ生活感がない。埃っぽさから只の空き室なのかもしれない。
そう分析した所で何が変わるわけでもない為に、音を立てないようにして障子を開く。
電気はついているものの、窓が遮断されているが為に今が何時なのか全く分からなかった。
ならばと窓を開くも結果は無情な物。