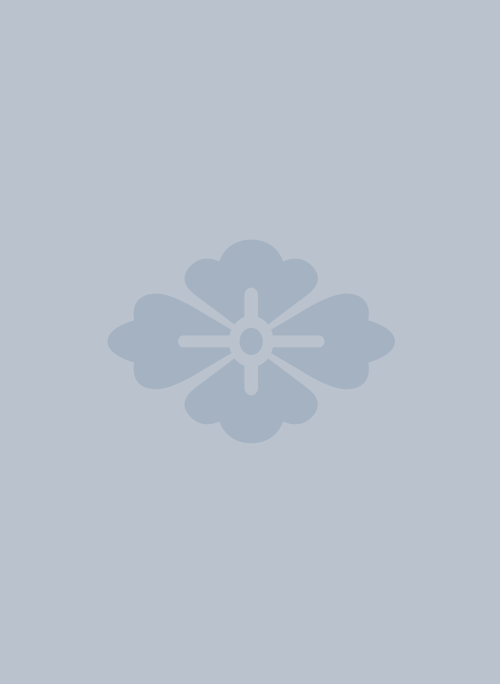「直斗を連れて、さっさと帰れ」
予定よりも、早めにやって来たシェリーに、僕は、言った。
……
僕は、大丈夫だって言ったのに。
すっかり風邪で調子を崩したと思ったらしい。
直斗は、シェリーに早く迎えに来いと電話をして。
僕を部屋に追いやった。
……これじゃ、どっちが子供なんだか、判らないじゃないか!
そう、頬を膨らませてみたけれども。
理由はともかく。
どっちにしろ、まともに動かないカラダに閉口して。
しぶしぶ、自分のベッドに身を預けた時。
直斗がシャワーを使う音を聞いて、彼が僕を一人にしてくれた、有り難さを思い知っていた。
実のところ……これは、かなり、まずい状態だ。
人間の本能に直結するような。
渇いた。
突き上げるような切なさは、ますますひどくなり。
それを、一人で慰めようとしても。
僕の部屋には、鍵が無く。
最中に、万が一、扉でも開けられたら、きっと、相手がだれでも止まらないんじゃないかと怖かった。
理性を吹き飛ばして、直斗を傷つけることだけは、嫌だ。
そんなことを思いながら、シーツを握りしめ、耐えているうちに、薬の副作用で、少し眠ったみたいだった。
「螢ちゃん?」
って言う、聞き慣れた声に、気がつくと。
目の前に、シェリーが、立っていた。