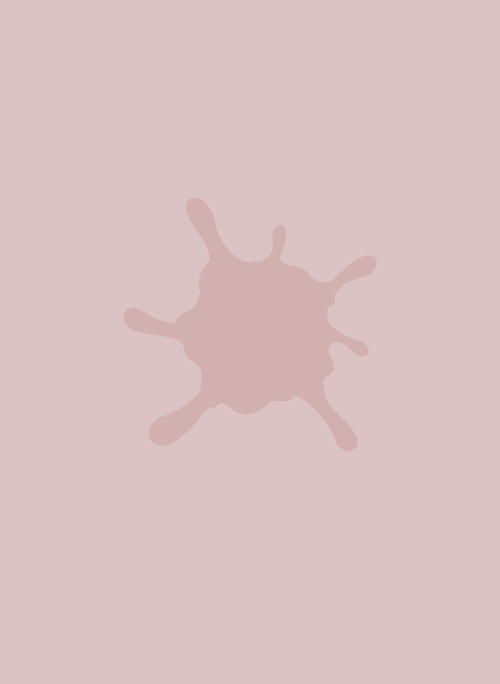゚*゚。*―*―*―*゚。゚*。゚。。
第壱章・過去
゚*゚。*―*―*―*゚。゚*。゚。。
文久2年。
まだ新選組が壬生浪士組という名で、
京都の守護に当たっていた頃。
その頃、私は京の民に歌うことを強いられていた。
なんでも私の歌は特別な力があり、私の歌を聞くだけで、
賭け事に強くなり、体力や治癒力が桁違いに上がるのだとか。
その為に、私は両親を亡くし、
長州の輩が血眼になって私を探していたり、
幕府の公家には保護という名の捕縛を受けたりしていた。
自分がどうなっても良かった。歌うことは好きだから、
構わないと。
でも勝手に歌を辞めれば、暴力と罵声の嵐だった。
疲れるのはそこだけ。
そんな日々から救ってくれたのが、壬生浪士組だった。
彼等は私を匿ってくれた。
壬生浪士組は優しい方も居たけれど、
権力を利用して、私の力を狙う者もいた。
正直言えば最初は信用出来なかった。
でも近藤様や土方様達は違った。
「珠姫君。おはよう。昨夜はよく眠れたかい?」
襖を開けて入ってきたのは、近藤勇。
近藤様はそうやって何時も私の体調を気遣ってくれた。
近藤様は、壬生浪士組の局長の1人で、
もう1人、私の苦手な芹沢鴨様という局長が居る。
近藤様とは違い、芹沢様は私の力が欲しいらしく、
会う度に歌を聞かせろと言われる。
答えなかったり、逆らったりすれば、
芹沢様はお気に入りの鉄扇で思いきり私を叩く。
それが非常に痛く、辛いものだ。
仕方なく歌うしか私には選択肢が無い。
「昨夜、芹沢局長が来ただろ?
歌っていたし、歌の質が違った。」
ガラリと襖を開けて来たのは、土方歳三。
彼もよく私を心配してくださる方だ。
「えぇ…よくご存知ですね?」
珠姫が純粋な問いかけをすると、
土方は頬を染め、視線をずらし答える。
「仕事をしていたからな…丁度聞こえてきたのだが、
なんだか悲しそうに聞こえたからな…」
彼は頭が良い上に、洞察力も優れている。