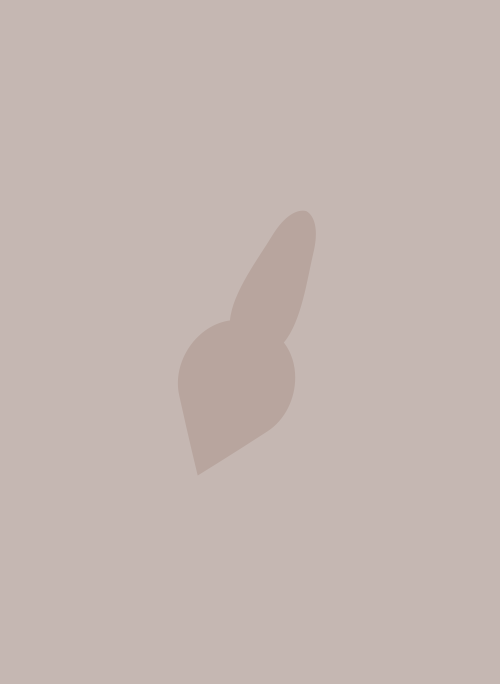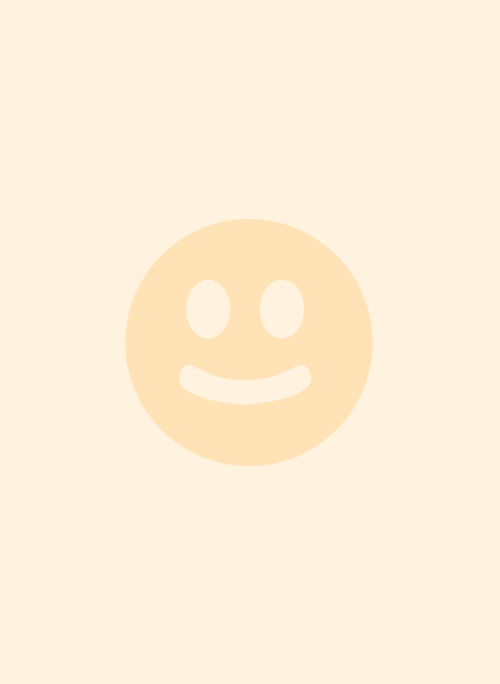突然、甲高い鳴き声が響いた。
放していた藤影が慌てた様子でりいの肩に戻ってくる。
そして油断なく周囲を警戒する。
ただならぬその様子にりいも松汰も口をつぐんで藤影を見つめた。
「…藤影?」
恐る恐るりいが問う。
その問いに対する答えは思わぬところから返ってきた。
「久しぶりだな、利花」
久々に聞く自分の本名。りいは弾かれたように振り向いた。
そこに立っていたのは痩身の若い男。
粗末な旅装束に身をを包み、背には荷物。
一見してただの行商人だが、ぼさぼさの前髪の下の眼光は異様なまでに鋭い。
その鋭さに覚えがあった。
「万尋(まひろ)様…」
りいは搾り出すように名を紡ぐ。
無意識に指が刀を求めて腰を探る。
それをみて万尋はにやりと口角を上げる。
「変わりねえようで何より。…といいてえ所だが、…ずいぶんと平和ボケしちまったみてえだ!」
突然投げられた符を、りいはすんでのところで叩き斬る。
どうやらただの牽制だったらしく、符はあっさりと燃え尽きた。
「…何の御用です!」
りいは松汰を庇うように一歩前に出る。
松汰はいまだに状況が掴めず目を白黒させていた。
「…お前の主の話だ」
「道満様!?」
りいは思わず声をあげた。
山に篭ると旅立ってから早一月以上経つのに、道満からは何の連絡もない。
さすがに心配だったのだ。
「聞きたいか」
「当然です!」
「…だが、ここではなんだ。ついて来い。もちろん一人で」
りいが頷きかけたとき、松汰が遠慮がちに袖を引いた。
「りいお姉…」
不安げなその声にりいの心が揺れる。
だがその瞬間、万尋がからかうような声を飛ばした。
「…なんだ。臆病風に吹かれて結界に引きこもってるだけならまだしも、さしで話もできねえのか。落ちたもんだな、利花?」
挑発と知りながらも、りいは万尋を睨んだ。
「参ります。…松汰、大丈夫。道摩の一族の仲間だ。藤影を頼むな」
松汰の頭を撫で、できる限り冷静な声を出す。
松汰は釈然としない表情だったが、頷いて藤影を抱えた。
放していた藤影が慌てた様子でりいの肩に戻ってくる。
そして油断なく周囲を警戒する。
ただならぬその様子にりいも松汰も口をつぐんで藤影を見つめた。
「…藤影?」
恐る恐るりいが問う。
その問いに対する答えは思わぬところから返ってきた。
「久しぶりだな、利花」
久々に聞く自分の本名。りいは弾かれたように振り向いた。
そこに立っていたのは痩身の若い男。
粗末な旅装束に身をを包み、背には荷物。
一見してただの行商人だが、ぼさぼさの前髪の下の眼光は異様なまでに鋭い。
その鋭さに覚えがあった。
「万尋(まひろ)様…」
りいは搾り出すように名を紡ぐ。
無意識に指が刀を求めて腰を探る。
それをみて万尋はにやりと口角を上げる。
「変わりねえようで何より。…といいてえ所だが、…ずいぶんと平和ボケしちまったみてえだ!」
突然投げられた符を、りいはすんでのところで叩き斬る。
どうやらただの牽制だったらしく、符はあっさりと燃え尽きた。
「…何の御用です!」
りいは松汰を庇うように一歩前に出る。
松汰はいまだに状況が掴めず目を白黒させていた。
「…お前の主の話だ」
「道満様!?」
りいは思わず声をあげた。
山に篭ると旅立ってから早一月以上経つのに、道満からは何の連絡もない。
さすがに心配だったのだ。
「聞きたいか」
「当然です!」
「…だが、ここではなんだ。ついて来い。もちろん一人で」
りいが頷きかけたとき、松汰が遠慮がちに袖を引いた。
「りいお姉…」
不安げなその声にりいの心が揺れる。
だがその瞬間、万尋がからかうような声を飛ばした。
「…なんだ。臆病風に吹かれて結界に引きこもってるだけならまだしも、さしで話もできねえのか。落ちたもんだな、利花?」
挑発と知りながらも、りいは万尋を睨んだ。
「参ります。…松汰、大丈夫。道摩の一族の仲間だ。藤影を頼むな」
松汰の頭を撫で、できる限り冷静な声を出す。
松汰は釈然としない表情だったが、頷いて藤影を抱えた。