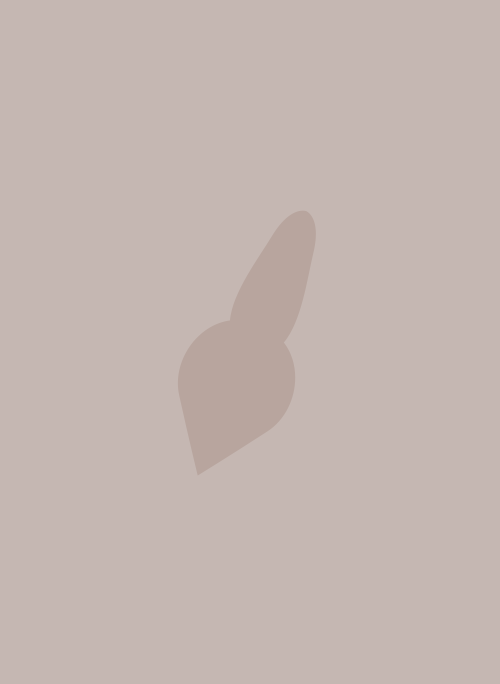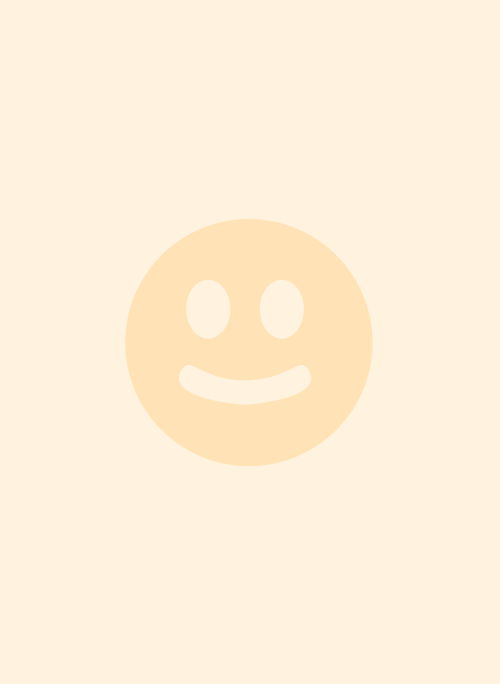「慣れてるとは思ってたけど」
先に口を開いたのは晴明だった。
「…俺と対等でいようとしてくれる人っていなかったから」
箸先を見つめたまま、独り言のようにこぼす。
「思ってたより、俺、臆病だ」
「…止せ」
りいもまた、膳から顔を上げずに遮った。
「そんな立派なものじゃない」
またも情けなさが込み上げてきて、ぎゅっと眉を寄せる。
「お前のことを理解できていたわけではない。それに…私だってお前の力は羨ましい。羨ましいさ」
術師としては誰もが羨むだろう。りいとて、晴明に嫉妬したことがないといえば嘘になる。
その才能は、彼が望んで手にしたものではないのに。
「私とて、変わらん」
絞り出すように告げると、晴明がくすりと笑った。
場違いにも思える笑い声に、怪訝なまなざしを向けると、晴明は愉しげにこちらを見ていた。
「…なんだ」
「いや、羨ましいって素直に言えるりいが、俺は羨ましい」
そんなことを言われても、と、りいは戸惑う。いつものようにからかわれているのか。
だが、晴明は笑うでもからかうでもなく、ゆっくりと言葉をつないだ。
「難しいことだよ。…俺は、できない」
本音を見せるなんて、できない。
寂しい呟きだった。
(…確かに)
晴明は、自分について多くを語らない。
口数は多いようでいて、中身のない会話か、りいのことにしか触れてこない。
これまでの会話の多くが、「りい」を主語にしていたな、と気付く。
だが。
先に口を開いたのは晴明だった。
「…俺と対等でいようとしてくれる人っていなかったから」
箸先を見つめたまま、独り言のようにこぼす。
「思ってたより、俺、臆病だ」
「…止せ」
りいもまた、膳から顔を上げずに遮った。
「そんな立派なものじゃない」
またも情けなさが込み上げてきて、ぎゅっと眉を寄せる。
「お前のことを理解できていたわけではない。それに…私だってお前の力は羨ましい。羨ましいさ」
術師としては誰もが羨むだろう。りいとて、晴明に嫉妬したことがないといえば嘘になる。
その才能は、彼が望んで手にしたものではないのに。
「私とて、変わらん」
絞り出すように告げると、晴明がくすりと笑った。
場違いにも思える笑い声に、怪訝なまなざしを向けると、晴明は愉しげにこちらを見ていた。
「…なんだ」
「いや、羨ましいって素直に言えるりいが、俺は羨ましい」
そんなことを言われても、と、りいは戸惑う。いつものようにからかわれているのか。
だが、晴明は笑うでもからかうでもなく、ゆっくりと言葉をつないだ。
「難しいことだよ。…俺は、できない」
本音を見せるなんて、できない。
寂しい呟きだった。
(…確かに)
晴明は、自分について多くを語らない。
口数は多いようでいて、中身のない会話か、りいのことにしか触れてこない。
これまでの会話の多くが、「りい」を主語にしていたな、と気付く。
だが。