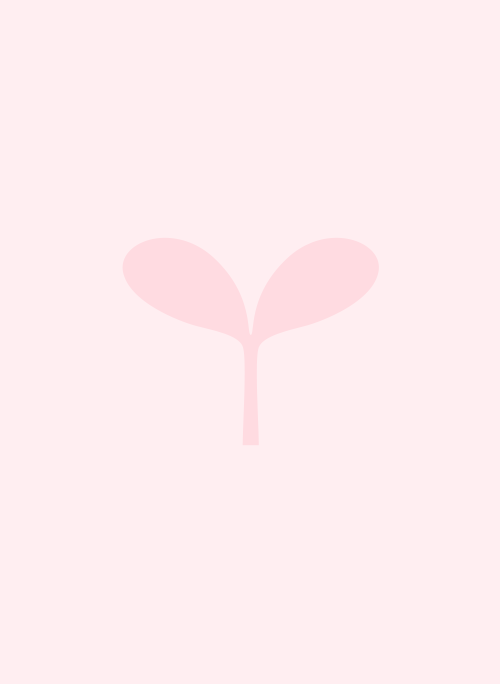多々良は腕を組んで、架妥たちの無事を祈った。
颪が義勇軍だと知ったのは、つい今朝だ。
出ていく前にぽろっと知らされ、なんの説明もないまま、ここで待たされている。
今、政府軍と戦っているであろうみんなの無事が心配で、心臓が痛い。
数、設備ともに、政府軍が有利だ。
山賊と農民で構成された義勇軍がどこまでやれるか。
お願いだ、神様。
みんなを…架妥を…殺さないで…!
多々良と同じように心を痛めながら、各家の中で父親を待っているだろう子ども達は、とても静かだ。
女達はいつも通りに家事をこなしている。
しかし、不安の色は隠しきれていない。
アジトは君が悪いくらいに静まり返っていた。
いつも眠そうに木の上で見張りをしている都楼は、いつもせっせと料理の下ごしらえをしている呉壽は、いつも素直でないながらも多々良に世話をやいてくれる架妥は…いない。
アジトがアジトではないような、
まるで異空間に紛れ込んだかのようだ。
多々良は一歩も動かずに、みんなが出ていった方向を見据えていた。
結局、その日、みんなは戻ってこなかった。