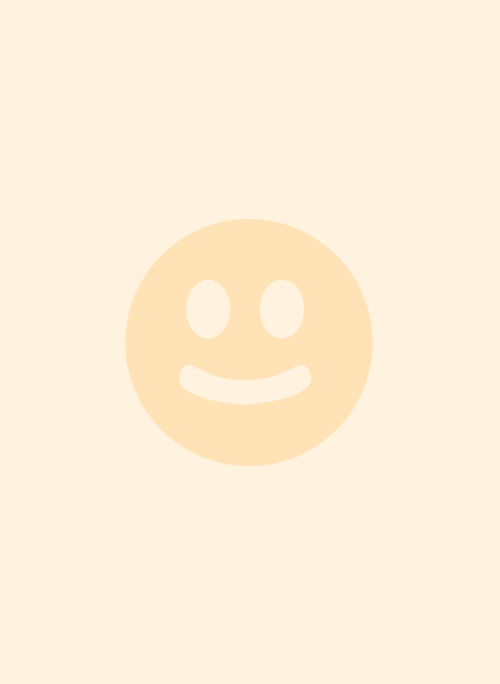夏の太陽に焦がされながら洞くつに足繁く通うわたしの努力は、日に日に虚しいものとなっていった。
つまり、ティートと会える時間がいよいよ減ってきたのだ。
彼の気持ちが移ろったわけではないことは、態度が変わらないことからもわかった。
なるべく会いに来ようとはしてくれているらしく、わたしはその言葉を信じていたし、実際、信じたその気持ちは決して虚しいものではなかった。
だが、なかなか洞くつに来られなくなっている理由を彼はどうしても語ろうとしなかった。
「シズに、心配をかけたくないから」
わたしの胸が心配で埋もれてしまうには、その言葉だけで十分だったのだが。
彼と自分とを隔てている存在を、全く知り得ぬままに日々は過ぎて行った。
もちろんそれを無視できていたわけではなかったけれども、同じ場所で同じような十幾年かを過ごしてきただけのわたしの乏しい想像力では、それらしい仮定の一つも立てることができなかったのだ。
彼が「忙しい」らしく、ひと時陸の世界にやってくる程の暇もない日が多いのだということ。
それは、ひとり浜辺で寂しい時間を過ごすことに耐えるには、あまりに乏しい情報だった。
つまり、ティートと会える時間がいよいよ減ってきたのだ。
彼の気持ちが移ろったわけではないことは、態度が変わらないことからもわかった。
なるべく会いに来ようとはしてくれているらしく、わたしはその言葉を信じていたし、実際、信じたその気持ちは決して虚しいものではなかった。
だが、なかなか洞くつに来られなくなっている理由を彼はどうしても語ろうとしなかった。
「シズに、心配をかけたくないから」
わたしの胸が心配で埋もれてしまうには、その言葉だけで十分だったのだが。
彼と自分とを隔てている存在を、全く知り得ぬままに日々は過ぎて行った。
もちろんそれを無視できていたわけではなかったけれども、同じ場所で同じような十幾年かを過ごしてきただけのわたしの乏しい想像力では、それらしい仮定の一つも立てることができなかったのだ。
彼が「忙しい」らしく、ひと時陸の世界にやってくる程の暇もない日が多いのだということ。
それは、ひとり浜辺で寂しい時間を過ごすことに耐えるには、あまりに乏しい情報だった。