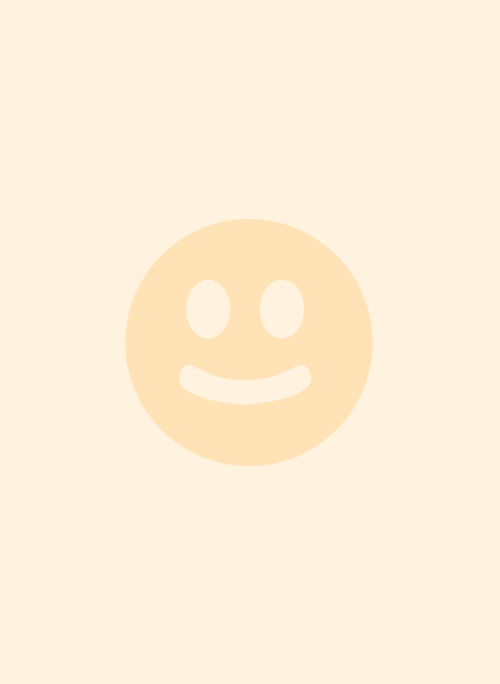次の日に、わたしがどきどきする胸を押さえ、こっそり家を抜け出して約束の場所へ行くと、彼は岩陰に座って、わたしを待っていた。
そう、会うなり本人が言ってきたのだ。
わたしたちは再会を喜び合って、くすくすと笑った。
この時のわたしぐらいの少女にとって、秘密などという言葉は、甘い響きを含んだものでしかなかった。
しかもこの秘密は、信じられないほどのうつくしさ、という、これまた少女にとっての甘い誘惑を伴ったものだった。
少女がうつくしいものを好むのは世の常だ。
「ばれなかった?」
「うん。もしばれたら、怪我をして動けなくなっている海鳥の世話をしに行くて言お思ってる」
「シズに嘘をつかせてしまうのは心苦しいけどね。仕方ない」
「大丈夫。ちゃんと、音を立てんように階段をおりてきたから」
わたしたちはお互いが知らなかったことを喋り合い、教え合い、相手の話したことを無限に吸収していった。
相手のことを知りたい、と思うとその容量は尽きるところがなく、わたしたちはお互いやお互いの住む世界についての知識をどんどん増やしていった。
少女の好奇心も、少年の好奇心も、底無しだったのだ。
そう、会うなり本人が言ってきたのだ。
わたしたちは再会を喜び合って、くすくすと笑った。
この時のわたしぐらいの少女にとって、秘密などという言葉は、甘い響きを含んだものでしかなかった。
しかもこの秘密は、信じられないほどのうつくしさ、という、これまた少女にとっての甘い誘惑を伴ったものだった。
少女がうつくしいものを好むのは世の常だ。
「ばれなかった?」
「うん。もしばれたら、怪我をして動けなくなっている海鳥の世話をしに行くて言お思ってる」
「シズに嘘をつかせてしまうのは心苦しいけどね。仕方ない」
「大丈夫。ちゃんと、音を立てんように階段をおりてきたから」
わたしたちはお互いが知らなかったことを喋り合い、教え合い、相手の話したことを無限に吸収していった。
相手のことを知りたい、と思うとその容量は尽きるところがなく、わたしたちはお互いやお互いの住む世界についての知識をどんどん増やしていった。
少女の好奇心も、少年の好奇心も、底無しだったのだ。