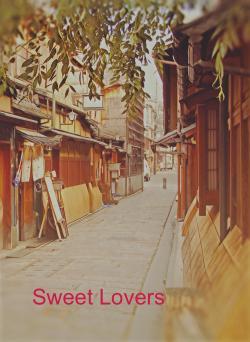お弁当の用意から、気合が入る。
ミツの分は私が作った。
家庭的なところ、アピールしないとね。
いつか。
誰かと結婚するとしても、いい奥さんになれないし。
ミツが小さい頃家族でよく来たという高原に到着。
「ねぇ、ハナ。
ここ、オレらの"秘密の場所"にしよ?
何か話すことあったら、ここに来て話すの。
ちょっとしたことでも、大事な話でも、何でもいいからさ。
合言葉は、"いつもの場所"でな。
これでお互いが分かるから。」
「うん!いいよ!
なんか秘密基地みたい!
この感覚、懐かしい!」
「……ガキ。」
「ガキって何よ!
ガキはないでしょ!
まだ全然大人っぽくはないけど、大人には近づいてるのに!」
私はミツの膝をポコポコ叩きながら言う。
「ゴメン。
冗談だよ。」
そう言ったとき、甘い空気をぶち壊すように、着信音が鳴り響く。
鳴ったのは、ミツの携帯だ。
「兄さんだ。
出ていい?」
「うん。」
私は、会話をあまり聞かないように、少し離れた。
「そ……それ、ホントなの兄さん!
今どこかって?
昔家族でよく来た高原だよ。
わかった!
ありがとう。」
いつも冷静なミツの声が慌てている。
「どうしたの?」
「ハナを嫌な目に遭わせた犯人が捕まったらしいんだ!
今から兄さんと宝月検事が犯人たち連れてくるって……
本当にソイツらか、確認してほしいんだって。
傷を抉ることになって悪いけど、って申し訳なさそうにしてたよ。」
「うん、いいよ別に。
ソイツらの顔拝んでボコボコにしてやりたいくらいだし。」
本当は、ボコボコにできるほど腕力なんてないし、武道とかもてんでダメだけど。
「ところでミツ、よくわかったよね。
あの日、私があんな目に遭ってるって。」
いつか私がミツとレンにあげた、星とハート、クローバーのブローチ。
あれにはテレパシー機能があったらしい。
……そんなの知らなかった。
ミツと話しながら、お弁当を広げる。
「……ハナ、美味いよ。
ハナは、結婚したら料理上手な、いい奥さんになりそう。」
っていうか、その漢字二文字はまだ早いよ。
そのワードは、成人と呼ばれる年齢に近くなってから出すものじゃないのかな?
そうは言うものの、ミツとの結婚生活を想像して、少し照れる。
どんな感じなんだろう、結婚、って。
「あ、ありがとう。
そう言われると嬉しい。」
食べ終えたお弁当を片付けているうちに、赤紫の車が、私たちの近くに停まった。
検察官をしているミツのお兄さんの車だ。
ミツの分は私が作った。
家庭的なところ、アピールしないとね。
いつか。
誰かと結婚するとしても、いい奥さんになれないし。
ミツが小さい頃家族でよく来たという高原に到着。
「ねぇ、ハナ。
ここ、オレらの"秘密の場所"にしよ?
何か話すことあったら、ここに来て話すの。
ちょっとしたことでも、大事な話でも、何でもいいからさ。
合言葉は、"いつもの場所"でな。
これでお互いが分かるから。」
「うん!いいよ!
なんか秘密基地みたい!
この感覚、懐かしい!」
「……ガキ。」
「ガキって何よ!
ガキはないでしょ!
まだ全然大人っぽくはないけど、大人には近づいてるのに!」
私はミツの膝をポコポコ叩きながら言う。
「ゴメン。
冗談だよ。」
そう言ったとき、甘い空気をぶち壊すように、着信音が鳴り響く。
鳴ったのは、ミツの携帯だ。
「兄さんだ。
出ていい?」
「うん。」
私は、会話をあまり聞かないように、少し離れた。
「そ……それ、ホントなの兄さん!
今どこかって?
昔家族でよく来た高原だよ。
わかった!
ありがとう。」
いつも冷静なミツの声が慌てている。
「どうしたの?」
「ハナを嫌な目に遭わせた犯人が捕まったらしいんだ!
今から兄さんと宝月検事が犯人たち連れてくるって……
本当にソイツらか、確認してほしいんだって。
傷を抉ることになって悪いけど、って申し訳なさそうにしてたよ。」
「うん、いいよ別に。
ソイツらの顔拝んでボコボコにしてやりたいくらいだし。」
本当は、ボコボコにできるほど腕力なんてないし、武道とかもてんでダメだけど。
「ところでミツ、よくわかったよね。
あの日、私があんな目に遭ってるって。」
いつか私がミツとレンにあげた、星とハート、クローバーのブローチ。
あれにはテレパシー機能があったらしい。
……そんなの知らなかった。
ミツと話しながら、お弁当を広げる。
「……ハナ、美味いよ。
ハナは、結婚したら料理上手な、いい奥さんになりそう。」
っていうか、その漢字二文字はまだ早いよ。
そのワードは、成人と呼ばれる年齢に近くなってから出すものじゃないのかな?
そうは言うものの、ミツとの結婚生活を想像して、少し照れる。
どんな感じなんだろう、結婚、って。
「あ、ありがとう。
そう言われると嬉しい。」
食べ終えたお弁当を片付けているうちに、赤紫の車が、私たちの近くに停まった。
検察官をしているミツのお兄さんの車だ。