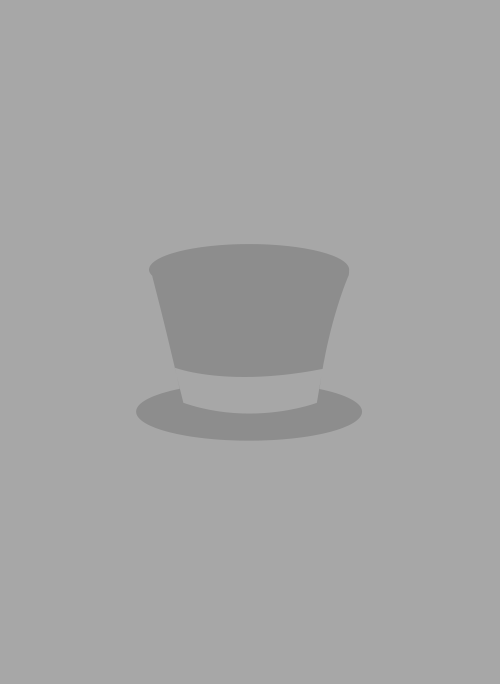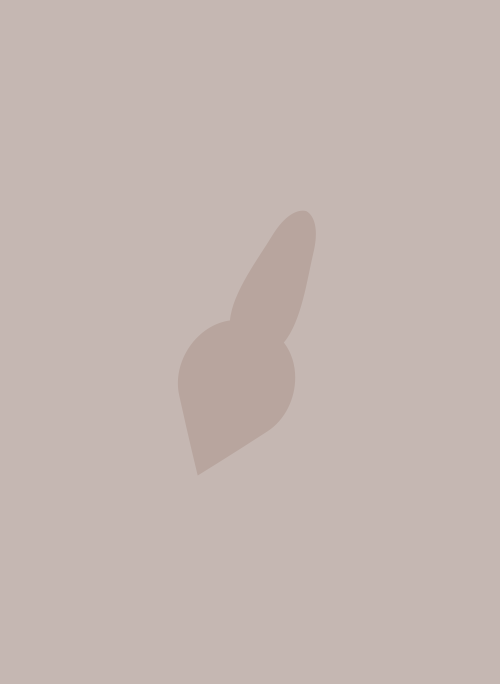家の中に入ると、サキはすぐさま旧式のストーブを点け、やかんを載せた。
俺は不器用そうなサキがいつかストーブをひっくり返してこの木造の一軒家を全焼させるんじゃないかと心配した。
やがてやかんからシュンシュンと湯気がたち、コタツに入っていた俺の前に
「インスタントですけど」とコーヒーの入った白いマグカップが出された。
「インスタントのほうが旨いこともあるさ」
サキはいつの間にか台所に立っていた。
「晩ごはん、食べていって下さい」
「おい、悪いよ。そこまで」
「これくらいしかクッキーのお礼できませんが」
サキの行動は素早かった。
みるみるうちにコタツの上には、見事な和食が並んだ。
「コンビニ弁当食ってんのかと思ってたよ」
「また意地悪言う。お腹空いたでしょう? 私はクッキー食べすぎたし」
サキの料理は旨かった。
きんぴらも、サバの塩焼きもしじみの味噌汁も。自家製なのか漬け物も。
準備していたのか玄米の飯も炊けていた。
コーヒーをすすりつつ、サキはおかわりを聞いてくる。
食卓の懐かしさ。
何故かそんな気持ちが浮かばない。
それは、これがサキとの初めての食卓だからだろう。
感じた気持ちは
懐かしさより幸福感だった。