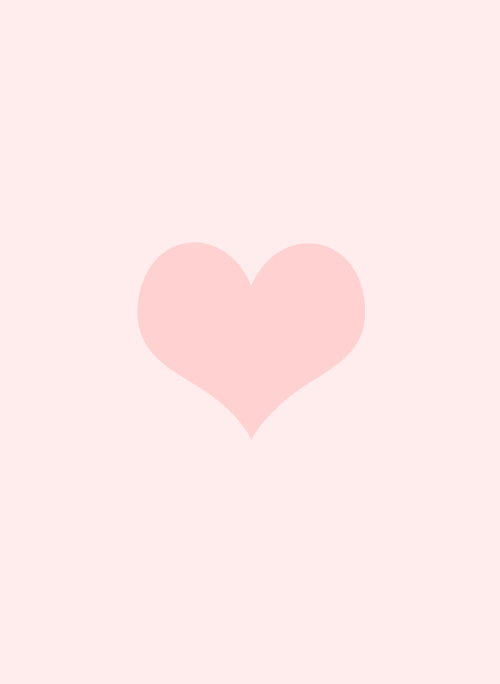〇
あたしにとって、彼女はお人形だった。綺麗な服を着て、いつでも絹糸のような髪を煌めかせ、ちょこんと、それでいて堂々とそこに在る、愛らしいお人形。
なだらかで膨らんでいない小さな胸、細い手足に大きな瞳と、花びらみたいな唇。指の間を流れていきそうな黒髪と、血色のいい肌。
なにより、言われたことの一から十までを従順に聞き入れる素直さ。
私は、彼女を天使だと思っている。人間界に降り立ち、あたしを慰めるためにお人形さんをやってくれる。水色のワンピースがとてもお似合いだった。
「聞いてくれる?」
とあたしの隣でブランコに座る彼女は言った。
「なにを?」
「男の人のこと」
「いやよ」
即答した。
「あたしといる時に、男の話なんてしないで」
脳裏にあの金髪不良が浮かんで、彼女と一緒にいるのに、こめかみが痛くなった。眉間にしわが寄る。
彼女はまだ小学六年生だ。教師として、その年代の心の成長は著しいものだと理解していても、彼女には、成長しないでもらいたかった。
ずっと、天使でいてもらいたいのだ。
だから少なくとも、あの不良のような男の話だけは、彼女の口からは死んでもご免だった。
あたしにとって、彼女はお人形だった。綺麗な服を着て、いつでも絹糸のような髪を煌めかせ、ちょこんと、それでいて堂々とそこに在る、愛らしいお人形。
なだらかで膨らんでいない小さな胸、細い手足に大きな瞳と、花びらみたいな唇。指の間を流れていきそうな黒髪と、血色のいい肌。
なにより、言われたことの一から十までを従順に聞き入れる素直さ。
私は、彼女を天使だと思っている。人間界に降り立ち、あたしを慰めるためにお人形さんをやってくれる。水色のワンピースがとてもお似合いだった。
「聞いてくれる?」
とあたしの隣でブランコに座る彼女は言った。
「なにを?」
「男の人のこと」
「いやよ」
即答した。
「あたしといる時に、男の話なんてしないで」
脳裏にあの金髪不良が浮かんで、彼女と一緒にいるのに、こめかみが痛くなった。眉間にしわが寄る。
彼女はまだ小学六年生だ。教師として、その年代の心の成長は著しいものだと理解していても、彼女には、成長しないでもらいたかった。
ずっと、天使でいてもらいたいのだ。
だから少なくとも、あの不良のような男の話だけは、彼女の口からは死んでもご免だった。