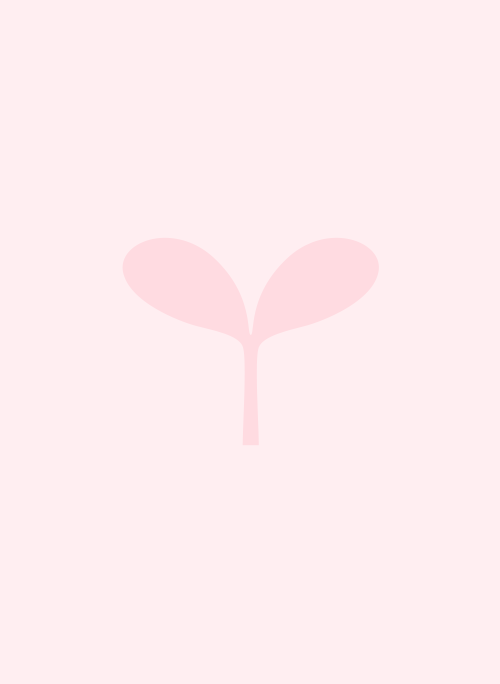「もっと、わかりやすく説明を……」
「ごちゃごちゃ言わずに、さっさと読め」
切実な要求をあっさりと切り捨てられ、ユーリは書類に目を落としながら、不満顔で呟いた。
「お芝居でのあなたの役割は?」
「俺は俺だ。生まれた時から演じている」
生まれた時から自分で自分の役を演じるだなんて、たちの悪い冗談だ。
「じゃあ復讐というのは?」
重ねて訊ねると、少年は煩そうに眉を潜めた。
「胸に手を置いて考えろ」
ようやく返ってきた言葉はただそれだけ。
眉をひそめたユーリは不毛な質問を打ち切って、真面目に文字を追うことにした。
「ごちゃごちゃ言わずに、さっさと読め」
切実な要求をあっさりと切り捨てられ、ユーリは書類に目を落としながら、不満顔で呟いた。
「お芝居でのあなたの役割は?」
「俺は俺だ。生まれた時から演じている」
生まれた時から自分で自分の役を演じるだなんて、たちの悪い冗談だ。
「じゃあ復讐というのは?」
重ねて訊ねると、少年は煩そうに眉を潜めた。
「胸に手を置いて考えろ」
ようやく返ってきた言葉はただそれだけ。
眉をひそめたユーリは不毛な質問を打ち切って、真面目に文字を追うことにした。