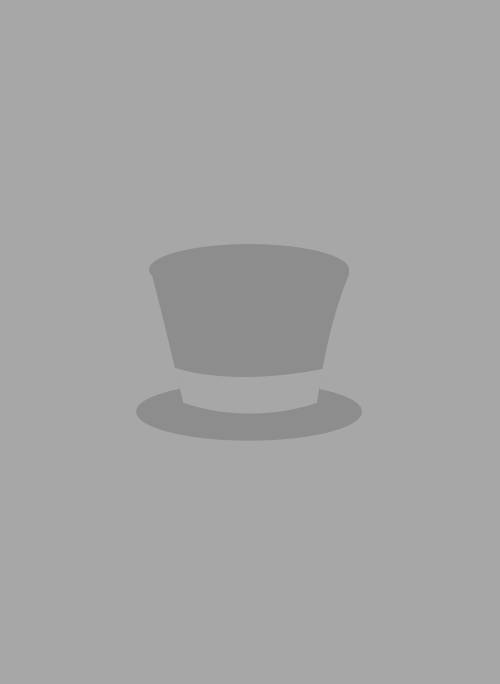碧(みどり)は走っていた。
歯を食いしばり懸命に腕を振るが腰が痺れ足が思う様に進まない。
何時のまにか衣服はボロボロに破れ肘や膝からは鮮血が吹き出しているが痛みは感じなかった。
『…何時もの夢じゃない』
頭では理解していても背後から忍び寄る例え様のない恐怖が碧の全身を包み込む。
夢だと分かっていても怖い物は怖い。
『助けて…助けてお母さん!』
後ろを振り返りたい衝動を押さえながら何処にも出口の無い闇をさまよっていた碧は不意に前方に小さな光があるのを見つけ、そこへと駆け込んだ。
(駄目!そこを覗いちゃ駄目)
もう一人の自分の声が天から聞こえるが、それとは逆に碧の体は吸い寄せられる様に光の穴へと近づく。
目を背けたくても、もはや体は金縛りにあった様に固く、背中に流れる冷たい汗が碧の悪寒を更に増幅させた。
歯を食いしばり懸命に腕を振るが腰が痺れ足が思う様に進まない。
何時のまにか衣服はボロボロに破れ肘や膝からは鮮血が吹き出しているが痛みは感じなかった。
『…何時もの夢じゃない』
頭では理解していても背後から忍び寄る例え様のない恐怖が碧の全身を包み込む。
夢だと分かっていても怖い物は怖い。
『助けて…助けてお母さん!』
後ろを振り返りたい衝動を押さえながら何処にも出口の無い闇をさまよっていた碧は不意に前方に小さな光があるのを見つけ、そこへと駆け込んだ。
(駄目!そこを覗いちゃ駄目)
もう一人の自分の声が天から聞こえるが、それとは逆に碧の体は吸い寄せられる様に光の穴へと近づく。
目を背けたくても、もはや体は金縛りにあった様に固く、背中に流れる冷たい汗が碧の悪寒を更に増幅させた。