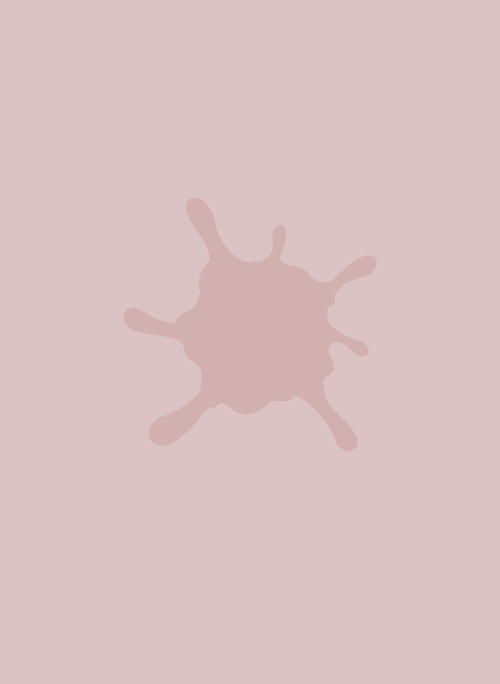翌日、ルーの言葉通り、吸血鬼になった二人の少女が目覚めていた。
目覚めた二人は、自分がなぜここにいるのか聞くこともなく、ハーゼオンの右と左にべっとりとくっついている。
私がハーゼオンに話しかけると、二対の眼差しが刺々しくこちらに向けられた。
ルーが慰めるように、私の肩をぽんと叩く。
「あれが血の魅了だから、気にすんな。うまく対象があいつに移って良かったよ。じゃなきゃ、一生もうどこにもいない主人を探してさ迷わなきゃならねぇからな」
「…あの人が、なんでルーの酷い扱いに怒らないのか分かった気がするわ」
何をするにも、ハーゼオンの傍を離れない二人の少女。
ハーゼオンは二人に優しい笑みを浮かべている。
「なんでもかんでも肯定されると分からなくなるんだとさ。自分がどこへ向かっているのか」
「だから、ルーはいちいち怒ってあげているのね」
私の言葉にルーが照れたように頬をかいた。
「まあ…。最近若干やり過ぎな気もしてるけど」
「何がやり過ぎだって?」
両脇に少女を従えたまま、ハーゼオンは私とルーのところへやって来る。
「なんでもねぇよ。帰るのか?」
「そうだね。目覚めた後に長居をすると、青の花嫁に迷惑をかけてしまいそうだし」
私を睨む二人の頭をハーゼオンは宥めるようによしよしと撫でた。
「次はちゃんと予定通りに来いよ。部屋を掃除しておいても、すぐ無駄になる」
「ははは、一ヶ月以内には行けるよう善処する。花嫁もまた今度ゆっくり話そう」
「えぇ」
両脇が私から引き離すようにハーゼオンの服を引っ張っている。
「…俺がまた、一人の時に」
ハーゼオンの苦笑に私も苦笑を返した。
「あの、その子たちを幸せにしてあげてね?」
私は一番気になっていたことを尋ねると、ハーゼオンは邪心なく笑った。
「もちろんだとも」