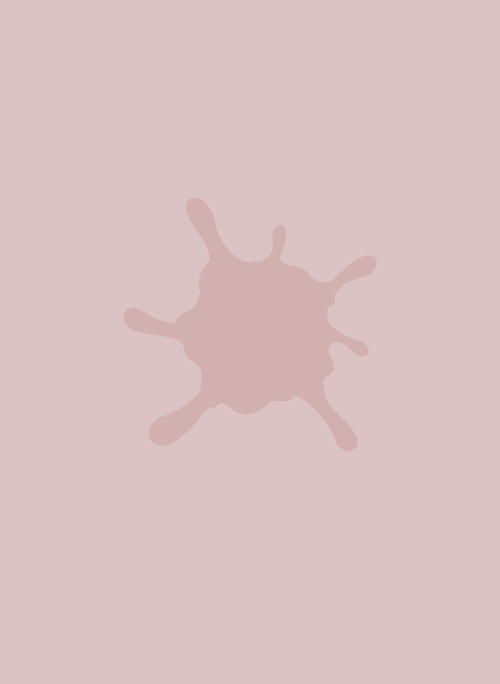ミルフィリアが帰り、疲れてぐったりとしているルーの隣に座った。
「有難う、ルー。そして気を遣わせてごめんなさい」
ルーはちろりと恨めしそうに私を見る。
「まったくだ。あの我が儘吸血鬼の相手は大変なんだからな」
「あら、でも我が儘なのはルーに対してだけなんじゃないのかしら?」
ミルフィリアはルーに対する時だけ、幼い顔をした。
わざと聞き分けのない子を演じて、気を引くかのように。
ルーが複雑そうに顔を歪めた。
「…あいつ、俺についてなんか言ってたか?」
「…え、ええと、その」
本人にばらしてもいいものなのだろうか。
私が悩んでいると、ルーが先手を取って口を開く。
「……。あいつが、俺を好いてることは知ってる」
淡々と明かされたのは、意外な事実だ。
「え、そうなの?」
「あいつも俺が知ってるってことを分かってるしな」
「それじゃぁ…」
なぜ気持ちに答えてあげないのだろうか。
二人共、分かっていて、何事もないかの風に装っているなんて。
隣のルーの表情は晴れやかなものではなかった。
「なあ花嫁。あいつ、何歳に見える?」
「十歳ぐらいだけど」
唐突な質問に、私は内心首を傾げる。
「だろ。…だけど俺は、外見が十四歳でも中身は違うんだよ。
実際はどうあれ、外見が十歳の奴じゃ、恋愛対象にならねぇ。俺にそんな趣味はない」
「あぁ…それで…」
ミルフィリアは、ルーの人としての倫理感が邪魔をすると言ったのだ。
「嫌いなわけじゃねぇけど。でも、無理だ。あいつはどこからどう見ても子供にしか見えないから。
せめて花嫁ぐらいの年頃だったらなぁ…」
後半は、ぶつぶつとルーが独り言のように呟いた。
声が小さすぎて、よく聞こえない。
「え?」
私が聞き返すと、ルーがはっと我に返った。
「…なんでもねぇ。
あのな、俺は誰かが誰かを好きになって、その誰かが同じ思いを返してくれるなんてことは、凄いことなんだと思う。
だからこそ、俺は同じ思いを返さなくてもいいんじゃないかって思ってる」