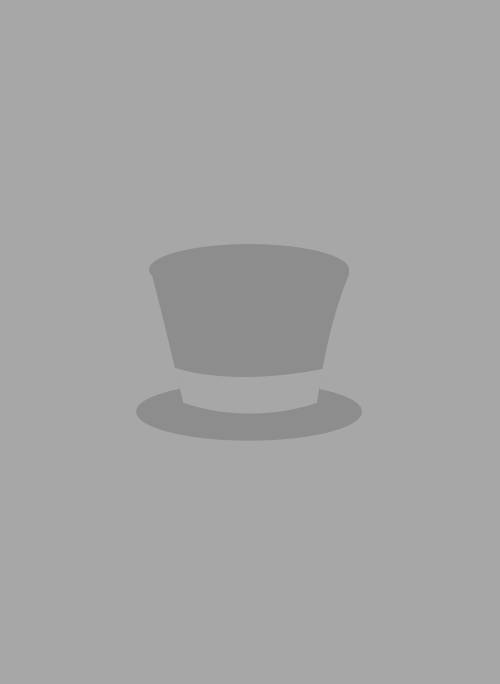ぺきり。
無意識なんだろう。彼はどこか遠くを見つめたまま、飲み干したスポーツドリンクのアルミ缶を片手で潰した。
タオルで乱暴に、額に浮かんだ汗を拭う。
潰れた青い缶を見て、あたしは思う。
彼はあんなに強くあたしを抱きしめたことはない。
「お前、潰れちゃいそうだなあ」
そう言って、逞しくて少しだけ日に焼けている腕にあたしを抱いて、暖かくて武骨な指で優しく優しくあたしに触れる。
もっと強く、ぎゅってして欲しいな。
あたしは青い缶を見て、そんなことを思う。
そんな簡単には潰れないよ。だから、だからあたしもぎゅってして。
そっと、彼の太ももに手をのせて擦り寄る。
「ん、どうした?」
彼は片手であたしの頭を撫でた。
ぺきり。
彼はもう一度、缶を握った。
ガコンっ!
そしてその缶を少し離れたごみ箱に捨てた。
やっぱり。
強く抱きしめてくれなくていい。
だからあたしを捨てないで。
あたしを抱き上げた彼の腕の中で、あたしは小さく鳴いた。
青いカンカン。