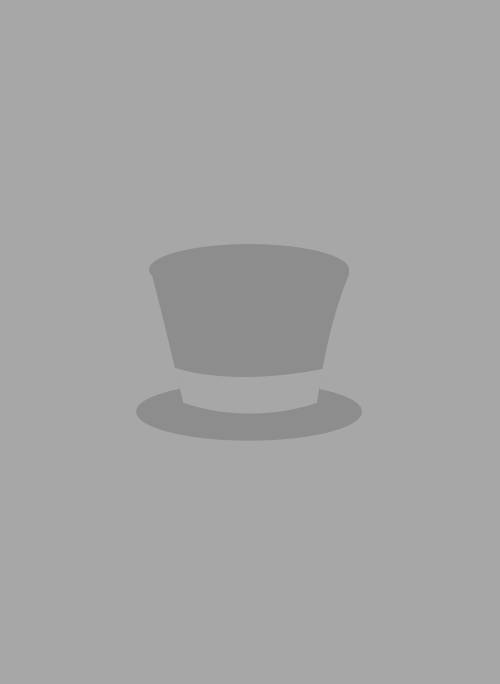君はいつも、古びたタオルに包まれて眠る。
もちろんきちんと洗濯してはいるけれど、何度も洗濯を繰り返したブルーはさらけたし、タオル地はふわふわ感を失って、肌ざわりはあんまり良くないタオル。
彼女の傍にあるのはいつもそのタオル。
「なんだか落ち着くの」
すでに眠りに落ちかけているのだろう。
瞳を閉じたまま、彼女は呟いた。
「このタオルはね、」
「大きくて、ごつごつしてて、暖かくてあなたの手みたいなの」
君が目を閉じていてよかった。
このにやけた顔はどうも見せられそうにない。
僕はそっと彼女の頬に手を伸ばした。
タオル。